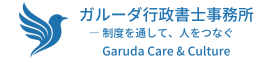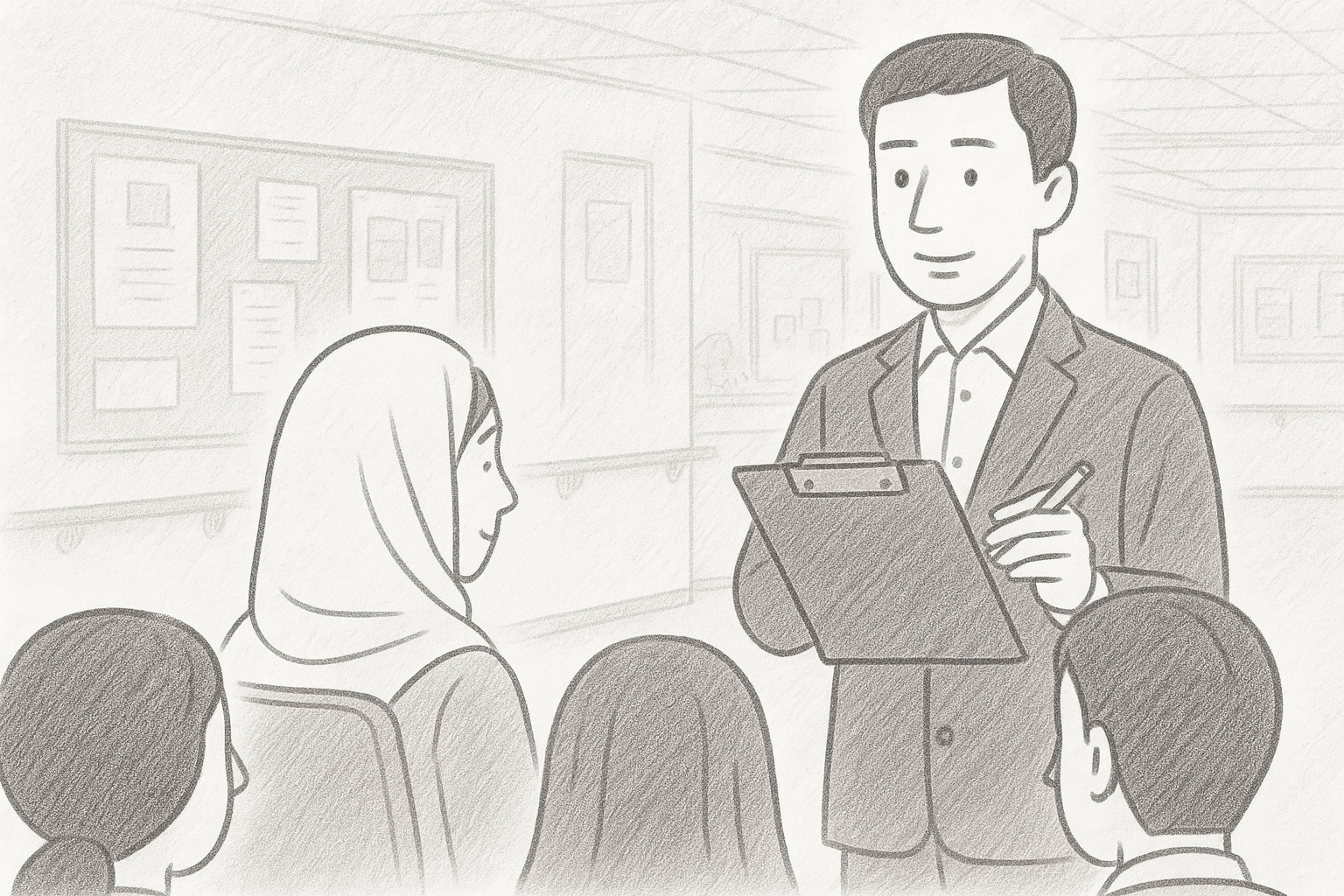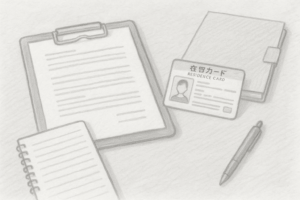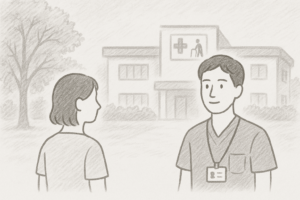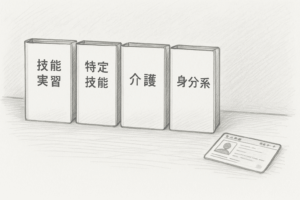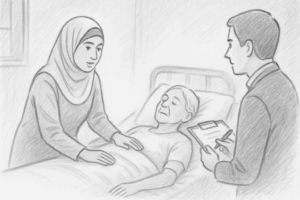特定技能で外国人介護人材を受け入れるとき、所属機関には数多くの義務と責任が課されます。所属機関とは介護施設や事業所そのものを指し、ここが制度上の「義務を履行する主体」です。言い換えれば、外国人材が安心して働けるかどうかは、所属機関の体制づくりにかかっています。
「人を採用するだけ」ではなく、「国に監督される立場になる」――これが特定技能制度の大きな特徴です。

特定技能は雇用契約を結んで終わりではありません。所属機関には多くの義務が課されています。



義務って聞くと正直不安です。もし守れなかったら、どうなるんでしょうか?



義務を怠れば行政指導や新規受入れ停止になる場合もあります。でも、準備さえ整えていれば問題ありません。制度を理解して運用する施設は、むしろ外国人材に選ばれる強い職場になりますよ。
労働条件に関する義務
所属機関がまず確認すべきは、労働条件の適正化です。
- 同等以上の報酬義務
日本人等が同じ業務に従事した場合と比べ、「きまって支給する現金給与額(超過労働給を含む)」を主軸に総額で同等以上であることが求められます。 - 労働・社会保険・租税法令の遵守
労働基準法や最低賃金法はもちろん、社会保険や税法に則って雇用を行うことが前提です。 - 社会保険等の加入
適用事業所であれば健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入しなければなりません。未加入は審査上の不適合や行政指導の対象となり得ます。



給与比較の基準って“基本給+手当”で考えればいいんですか?



給与の比較は“毎月きちんと支払う給料の部分(基本給や時間外手当など)”が基準になります。通勤手当や住宅手当のような実費補助は別枠で扱われます。
雇用契約と書面化の義務
所属機関は、外国人材と雇用契約を結び、その内容を必ず書面で交付しなければなりません。
- 契約書には、業務内容、勤務時間、休日、賃金、残業代の計算方法など主要条件を明記します。
- 契約の変更・終了・新規締結は、所属機関の随時届出の対象です。法務省令で定める軽微な変更を除き、事由発生日から14日以内に提出が必要です。



“ちょっとした変更だから”と口頭で済ませるのは危険です。軽微な変更かどうかは運用要領の一覧表に基づいて判断すべきです。



じゃあ週5日勤務を週4日にするのも軽微じゃないですよね?



はい、それは随時届出対象です。14日以内に必ず処理しましょう。
生活支援に関する義務
特定技能介護の大きな特徴は、生活支援の実施が所属機関の義務となっている点です。
支援計画には以下の項目が含まれます。
- 住居の確保(寮やアパートの手配)
- 入国直後の支援(空港送迎、役所同行、銀行口座、携帯契約など)
- 生活オリエンテーション(ゴミ出し、交通機関、医療機関の案内)
- 日本語学習の支援(教材提供、学習機会の確保)
- 通訳・翻訳体制の整備
- 相談窓口の設置
これらの支援に要する費用は、外国人本人に負担させることが禁止されています。



登録支援機関に委託できますが、責任は所属機関に残ります。“丸投げ”はできません。
届出と報告の義務
所属機関には、外国人材の状況を国に届け出る義務があります。
- 定期届出
2025年改正で制度が変更され、前年分を毎年4月1日から5月31日までに提出する年1回方式となりました。 - 随時届出
契約の変更・終了・新規締結、支援計画や委託契約の変更・終了などが発生した場合、法務省令で定める軽微な変更を除き、事由発生日から14日以内に提出します。
介護分野特有の義務・制限
介護分野には、他分野にはない特有の要件があります。
受入人数の上限
「日本人等の常勤介護職員の総数以内」であることが条件です。看護師や事務職は含まず、介護を主たる業務とする常勤職員を基準にします。
この人数要件は、介護サービスの質を維持するための“支援体制バランス基準”として設けられています。
「日本人等の常勤介護職員の総数以内」とは、介護を主たる業務とする常勤職員(常勤換算ベース)を基準とし、看護師や事務職員など介護以外の職種は含まれません。
特定技能「介護」は、職場全体での日本人職員による指導・監督体制の確保を前提としており、この人数枠を超える受入れは、支援能力が不足していると判断され、許可対象外となります。
職務範囲の限定
特定技能「介護」が従事できるのは、介護業務および付随的な関連業務に限られます。調理・清掃・送迎などの専従は不可ですが、介護に付随する範囲であれば可能です。
訪問系サービスの従事(2025年改正)
2025年3月31日の厚労省通知により、特定技能「介護」は訪問介護サービスにも従事可能となりました。ただし、従事前に巡回訪問等実施機関の確認を受け、その後も巡回確認を受ける義務があります。体制を整えたうえで初めて訪問系サービスに配置できる点に注意が必要です。
特定技能「介護」の従事前には、巡回訪問等実施機関による「体制確認」を受け、その後も定期的な巡回確認を受ける二段階の仕組みが設けられています。
この確認は、利用者と外国人介護職員が1対1で業務を行う訪問系サービスにおいて、適切な指導・監督体制と権利保護を担保するための制度的安全弁です。
「所属機関が勝手に判断して配置する」ことは認められず、確認を経ずに従事させた場合は改善指導の対象となります。



その“巡回訪問等実施機関”って何ですか?



簡単にいうと、訪問介護の現場を外部からチェックする第三者機関です。事業所が特定技能の人を訪問系に従事させる前に、その体制が整っているかを確認してくれます。その後も定期的に巡回して、支援がきちんと行われているかチェックします。



なるほど。つまり、うちだけで判断して『明日から訪問介護OK』とはできないんですね。



そうです。必ず事前確認を受けて、巡回でもフォローされる仕組みです。安全性を確保するために導入されたルールだと思ってください。
技能試験・日本語要件
介護技能評価試験+介護日本語評価試験の合格が必要です。日本語はJLPT N4以上またはJFT-Basic。技能実習2号(介護)を良好に修了した者は免除されますが、非介護分野での修了者は介護日本語の免除はありません。所属機関には「介護日本語」の習得支援を行う義務が強調されています。



どうして介護だけ人数制限や特別な日本語試験があるんですか?



介護は人命に関わる仕事だからです。人数枠は支援体制を崩さないため、日本語要件は現場で安全にコミュニケーションを取るために定められています。
所属機関変更や退職時の義務
外国人材が退職・転職する場合、所属機関には次の責任があります。
- 契約終了に関する随時届出(14日以内)
- 書類の提出と保管。適切な保管が求められる。
退職・転職は日常的に起こります。だからこそ期限内の届出と、書類を適切に保管しておくことが重要です。
違反した場合のペナルティ
義務を怠ると、所属機関は次のような監督措置を受ける可能性があります。
- 行政指導や改善命令
- 新規受入れの停止
また、労働条件・生活支援・届出などいずれかの義務が不十分な場合、更新や新規の許可申請において不許可や補正指導のリスクがあります。特に生活支援は外国人材の定着に直結するため、審査でも重点的に確認される項目です。
不法就労を防ぐ義務と、雇用者側のペナルティ
特定技能「介護」の受入れでは、在留資格の有効性と活動範囲の管理が所属機関の実務責任です。
更新漏れや届出遅延により、本人が資格外活動状態になると、不法就労扱いとなる場合があります。



“うっかり勤務継続”でも、雇用主側の責任は問われます。更新期限と在留カードの写し管理を習慣にしましょう。



「本人に任せきりじゃなく、施設側で確認するんですね。
入管法第73条の2(不法就労助長罪)は、在留資格がない外国人を雇用した場合に「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」を科すと定めています。



実は、“うっかり雇用”しても処罰対象になる可能性があるんです。



えっ、本人じゃなくて、うち(事業者)がですか?それ、こわい……。



そうです。入管法第73条の2(不法就労助長罪)は、在留資格のない外国人を雇用・あっせんした事業者側に対して、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すと定めています。
つまり、『知らなかった』『更新中だと思っていた』では免責されません
この罪が適用されるのは、たとえば――
・在留カードの有効期限が切れているのに勤務を続けさせた場合
・資格外活動にあたる業務をさせた場合(たとえば清掃や送迎の専従)
など、現場でよく起こる“確認漏れ”でも該当することがあります。



罰金だけでなく、事業者としての信頼や今後の受入れ許可にも影響します。だから、雇用主が主体的に在留資格を管理することが大切なんです。



つまり、本人の責任じゃなくて、施設の管理責任なんですね。
また、雇入れ・離職時の「外国人雇用状況届出」(職業安定法第28条)の不履行にも罰金規定があります。
このような法的責任は、所属機関の信頼や新規受入れ審査にも影響します。
在留資格管理は“行政対応”ではなく“雇用管理”の一部と考えることが重要です。
実務上のチェックポイント
所属機関に課される義務は多岐にわたります。
大事なのは、書類を一度揃えただけで満足するのではなく、日常の運用でちゃんと実践できているかを国から確認される点です。
特に抜けやすいのは届出期限や生活支援の中身。
以下を定期的に確認することで、監督指導や不許可リスクを防げます。
✅在留資格・在留期間・在留カード記載内容を確認しているか
雇用前に在留カードの原本を確認し、写しを保管すること。在留資格欄が「介護」であるか、在留期限が有効であるかを確認する。誤った資格での雇用は不法就労助長罪(入管法第73条の2)の対象となる。
✅在留カードの有効期限を定期的に確認し、写しを保管しているか
更新・変更中の従業員については、資格外活動とならないよう勤務を調整し、更新受付票等を保管しておく。
✅外国人雇用状況届出(ハローワーク)を提出しているか
雇入れ・離職時には職業安定法第28条に基づき「外国人雇用状況届出」を提出する。入管届出とは別の義務であり、どちらも必要。
✅雇用契約書を作成・交付しているか
契約内容を明文化し、書面を本人に交付する。未交付や記載不備は不許可・補正指導の原因となる。
✅報酬は「きまって支給する現金給与額」で日本人等と同等以上か
比較対象は基本給・時間外手当などの現金給与額。通勤手当や住宅手当など実費補助は含まれない。
✅労働・社会保険・租税法令に適合しているか
労働基準法・最低賃金法・社会保険・税法に適合していること。未加入や法令違反は不適格判断の対象。
✅適用保険に加入させているか
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に適用事業所として加入させる。未加入は制度理解不足と見なされる。
✅生活支援計画を作成・実施しているか
支援内容を計画書に基づき実施し、実施記録を残す。費用を外国人本人に負担させることは禁止。
✅随時届出(軽微な変更を除き14日以内)、定期届出(前年分を翌年4/1~5/31)を期限内に行っているか
期限超過は新規受入れ・更新に影響する。届出の遅れは制度不履行と扱われる場合がある。
✅日本人等の常勤介護職員総数を超えていないか
受入上限は日本人等の常勤介護職員総数以内(要領別冊介護2025/4/21 p.4)。看護職・事務職は含まれない。
✅職務範囲が介護業務+付随業務に限定されているか
清掃・送迎などの専従は不可。介護に付随する範囲でのみ従事可能。
✅訪問系サービスの従事前確認・巡回確認を受けているか
訪問系サービスに従事させる前に、巡回訪問等実施機関の確認を受け、その後も定期的に巡回確認を受ける(厚労省通知2025/3/31・要領別冊介護2025/4/21)。
✅退職・転職時に随時届出を行い、書類を適切に保管しているか
契約終了から14日以内に届出を行い、関連書類を適切に保存しておく。
ケーススタディ
Case1:随時届出の遅れ
ある特養では、外国人介護職員が自己都合で退職しました。担当者は多忙のあまり届出を後回しにしてしまい、気づけば退職から3週間。14日以内の随時届出義務を逸脱してしまい、入管から「改善指導」を受けました。その後、追加で新たに採用しようとした外国人材の在留資格変更申請で、不許可リスクを指摘される結果になりました。届出の遅れが次の採用に直結する、典型的な“連鎖トラブル”です。
Case2:生活支援不足による早期離職
ある施設では、採用後のフォローを現場任せにしてしまい、日本語学習の時間も取れず、相談窓口も形だけ。外国人職員は仕事の相談もできず孤立感を深め、数か月で退職しました。事業者にしてみれば「人手不足の解消」と思って採用したのに、逆に職場の雰囲気が悪化。後に残った職員からも「サポートがないのにまた外国人を入れるのか」と不信感が募りました。生活支援は“机上の制度”ではなく“定着の鍵”だと痛感させられるケースです。
Case3:職務範囲の逸脱
慢性的な人手不足に悩む小規模施設で、特定技能介護職員に送迎や清掃を専従させてしまいました。入管からの確認で「付随業務の範囲を超えている」と指摘され、改善命令に。本人は「介護をしたい」との目的で来日しているため、モチベーションも低下。結果的に早期退職につながりました。現場は「人が足りないから」と思っても、職務範囲を外れると本人にも施設にもリスクとなります。
Case4:報酬の扱いを誤ったケース
ある施設は「通勤手当も含めれば日本人と同等額」と考えていましたが、比較対象である日本人と同等額とは「きまって支給する現金給与額」であることを理解しておらず、不適切と判断されました。その結果、更新申請で補正を求められ、再提出に。現場では「手当を全部足せばいいんじゃないの?」と誤解しやすい部分ですが、制度上の定義を押さえておかないと大きな手戻りになります。
Case5:訪問系サービスでの運用ミス
訪問介護に外国人を従事させたものの、従事前の巡回訪問等実施機関による確認を受けていなかった事例。巡回確認でも体制不備が判明し、改善指導を受けました。本人は「現場に入ったのに後からダメと言われた」と困惑し、利用者家族も不安を抱く結果に。訪問系サービスは解禁されたとはいえ、事前確認の手続を欠かすと現場が混乱します。
Case6:更新漏れに気づかず勤務継続 ― 不法就労助長罪に発展しかけた例
ある介護施設で、特定技能「介護」の職員が在留期間の更新申請を忘れたまま勤務を続けていた。
人事担当者は「本人が申請していると思い込んでいた」が、実際には申請がなされておらず、在留期限を1か月過ぎて勤務していたことが後日判明。入管庁から「不法就労の可能性あり」として調査通知が入り、施設管理者は事情聴取を受けることとなった。幸い、すぐに勤務停止と自主報告を行ったため刑事告発は免れたが、
施設は「不法就労助長罪(入管法第73条の2)」に該当するおそれがあるとして厳重注意処分を受け、半年間の新規受入れ停止措置を受けた。
今後の改正を見据えて
特定技能制度は今後も変わり続ける可能性があります。たとえば、
- 生活支援の範囲拡大
- 日本語教育支援の強化
- ICT活用や地域連携義務化の議論
といった項目が議論されています。これは「将来の見通し」であり、まだ確定していない部分です。したがって現場では“検討されているテーマ”として把握する程度にとどめつつ、今から少しずつ準備を始めておけば、改正が実際に来たときに慌てず対応できます。最新の公式資料の更新確認も欠かせません。
まとめ
所属機関の義務は「労働条件」「生活支援」「届出」に加え、介護分野特有の要件(人数枠、職務範囲、訪問系サービス、日本語支援)が大きな特徴です。これらを徹底することは、外国人材に安心して働いてもらうための基盤であると同時に、所属機関自身の信頼性や持続的な人材確保につながります。
義務を守ることは“行政への対応”にとどまりません。外国人材から“安心して働ける職場”と評価されることは、採用競争力にも直結します。つまり、法令遵守はコストだけではなく“投資”でもあります。最新の制度に沿って誠実に運用していくことが、最終的には組織の安定経営や地域社会からの信頼にもつながります。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)