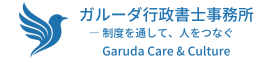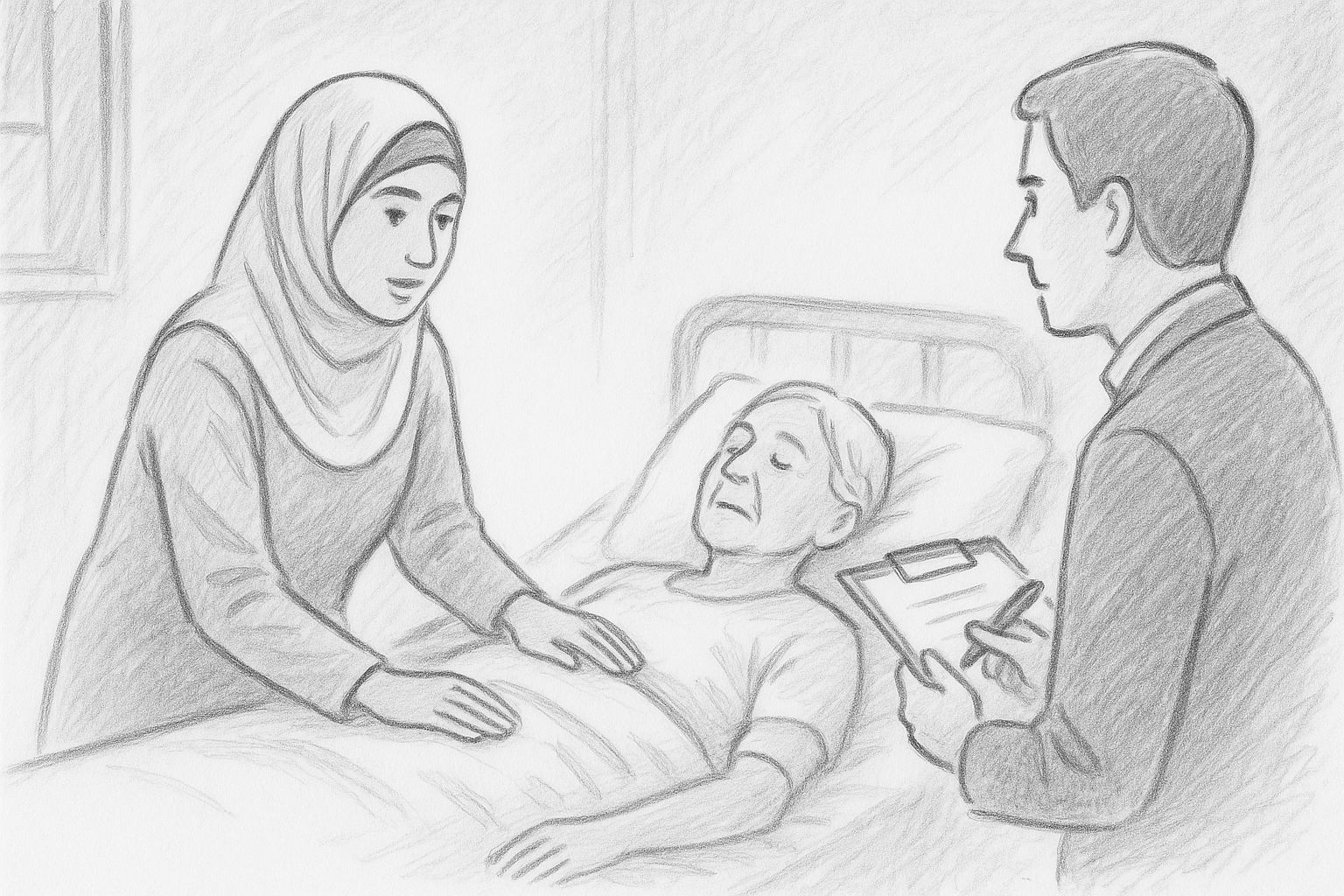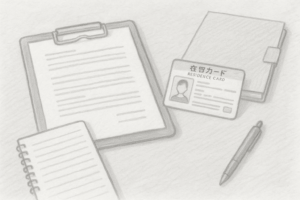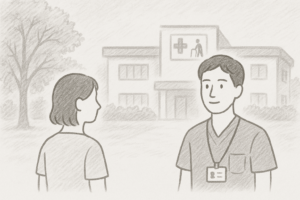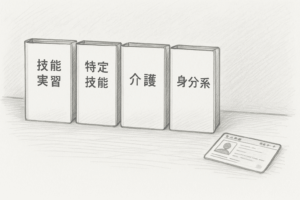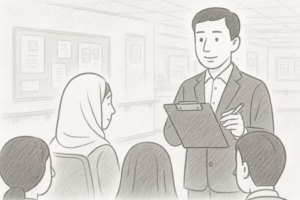特定技能「介護」を取得するには、日本語能力試験に合格するだけでなく介護技能評価試験にも合格することが必要です(または、介護福祉士養成施設を修了している場合には代替可能とされています)。
この試験は「利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル」を確認するものとされ、合格者は「即戦力となる知識・経験を有する」と評価されます。
すなわち、特定技能「介護」として日本で働ける人材かどうかを振り分ける制度上の関門の役割を担っているのです。
試験の概要と形式
介護技能評価試験は CBT方式(Computer Based Testing) により、パソコン画面上で出題されます。シナリオ形式の問題が中心で、利用者や職員の発言を読み取り、その場面で最も適切な対応を選択します。
出題範囲と特徴
出題は介護の主要な業務領域から幅広く設定されています。
- 身体介護:入浴・排泄・食事介助など
- 生活支援:掃除・洗濯・調理・買い物支援
- 認知症ケア:声かけ方法、行動理解、事故防止
- 緊急対応:転倒や体調変化への初期対応
- 記録理解:介護記録の読み取り・判断
単なる知識暗記ではなく、状況理解と判断力を組み合わせて解答する必要があります。

暗記で済む試験ではないんですね。



その通りです。例えば“寒い”と訴える利用者に、毛布を掛けるのか、体温を確認するのか、状況によって正しい判断は変わります。そうした現場対応力が問われる試験なんです。
出題言語と日本語能力との関係
運用要領では、試験言語は「実施国の現地語」と規定されています(国内実施の言語については実施要項を参照)。
ただし、出題は日本の介護現場を想定しており、利用者とのやりとりや記録に関する設問も含まれるため、実際には一定の日本語理解力がなければ合格は難しいのが現実です。
実施機関と受験ルール
介護技能評価試験の実施主体は、運用要領で「厚生労働省が選定した機関」と定められています(運用要領2025/4/1改正)。実際の運営は、厚労省の選定を受けた機関が担い、国内外での試験実施はJICWELS(国際厚生事業団)と試験実施会社プロメトリックを中心に行われています。
海外における日本語関連試験の実施については、国際交流基金(Japan Foundation)が関与しているケースもあります。ただし、法令や運用要領に明記されているのは「厚労省選定機関」であり、関与機関の詳細は公式の試験要項や告知を確認してください。
受験料(日本国内で7,000円)や再受験の「45日ルール」などの具体的な受験条件は、JICWELSが公表する最新の受験要項に基づきます。そのため、受験を予定する場合は必ず最新の要項を確認してください。
合格率
- 介護技能評価試験:45問前後、60分、合格基準60%以上(従前通り)



不合格のあとすぐ再挑戦できないんですね。



はい。JICWELSの要項では45日間の再受験制限があります。だから施設側も採用スケジュールを考えるときは、このブランクを見込んで計画する必要があります。
学習と対策
公式サイトにはサンプル問題が公開されており、受験者は事前に出題形式を確認できます。市販の参考書や模擬試験も利用可能ですが、最も有効なのは 現場シナリオを現地語・日本語の両面で理解し対応できる訓練 です。
施設側がロールプレイ研修や日本語OJTを組み合わせると、受験者はシナリオ型問題に強くなり、合格率も高まります。
試験対策の実際
試験対策は制度上の義務ではありませんが、現場ではさまざまな主体が自主的に支援を行っています。代表的な形は次のとおりです。
- 送り出し機関や日本語学校での教育(母国)
入国前に候補者を教育することが最も一般的です。フィリピンやインドネシアでは、送り出し機関が介護技能試験対策コースを提供し、日本語学校と連携して介護用語や場面対応を事前に学ばせています。 - 公式教材とサンプル問題の活用
JICWELSの公式サンプル問題が公開されており、受験者はこれを使って出題形式に慣れることができます。 - 民間教材・講座
市販テキストやオンライン模擬試験を利用するケースも多く、教育機関が模擬試験サービスを有償で提供することもあります。 - 受け入れ施設や登録支援機関による研修(国内)
国内で試験を受けられるのは、既に留学や技能実習など他の在留資格で滞在している外国人です。こうした候補者が特定技能「介護」への資格変更を目指す場合、受け入れ施設や登録支援機関がフォローを行うことがあります。



結局、誰が試験対策を担うんですか?



必ずしも一元的に決まっていません。母国では送り出し機関や日本語学校が中心ですが、日本に既に滞在している候補者には施設や登録支援機関がフォローすることもあります。つまり、複数の主体が状況に応じて分担しているんです。
未経験者でも合格できるのか?
介護技能評価試験は、介護の実務経験がなくても合格できる内容になっています。運用要領でも「実務経験を前提とせず、知識と判断力を確認する試験」と位置づけられています。
合格者は制度上「即戦力となる知識・経験を有する」とみなされます。ただし、ここでいう即戦力とは 在留資格を与えるに足る基準を満たした という意味であり、現場で日本人介護職と同じレベルで働けることを直ちに保証するわけではありません。
実際の勤務では体力・観察力・応用的な判断が不可欠であり、受け入れ施設によるOJTや生活支援が欠かせません。



経験がなくても試験に受かるなら、すぐに現場で働けるんでしょうか?



技能試験は基礎知識の確認で、制度上は即戦力と評価されます。ただ、現場で本当に戦力になるには研修やフォローが欠かせません。ここをどう支援するかが施設側の大きな役割なんです。
まとめ
介護技能評価試験は、介護知識や判断力を測るだけでなく、それを「現地語(国内は要項参照)で理解し回答できるか」を確認する試験です。これは制度上の関門であり、現場の安全性と質を担保するために不可欠な仕組みです。
2025年3月31日の厚労省通知により、訪問系サービスへの従事が一部解禁されることが決まりました。利用者宅でのサービスは、施設以上に「一人で判断する力」と「即応力」が問われる領域です。その意味で、介護技能評価試験の重要性は今後さらに増すでしょう。
合格はゴールではなく、外国人材が現場で長期的に活躍するための第一歩です。受け入れ施設は試験支援と勤務後の研修を一体的に考え、多文化共生の介護現場を築くことが求められています。
介護技能評価試験に合格しても、その先には在留資格の申請や受け入れ施設との契約、支援計画の届出など、多くの法務手続きが待っています。行政書士は、こうした制度上の要件を確実に整え、合格から就労までの橋渡しを行います。制度や書類の準備で不安がある場合は、入管専門の行政書士にご相談いただくことで、スムーズかつ安心して手続きを進めることができます。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)