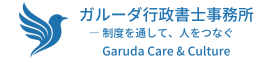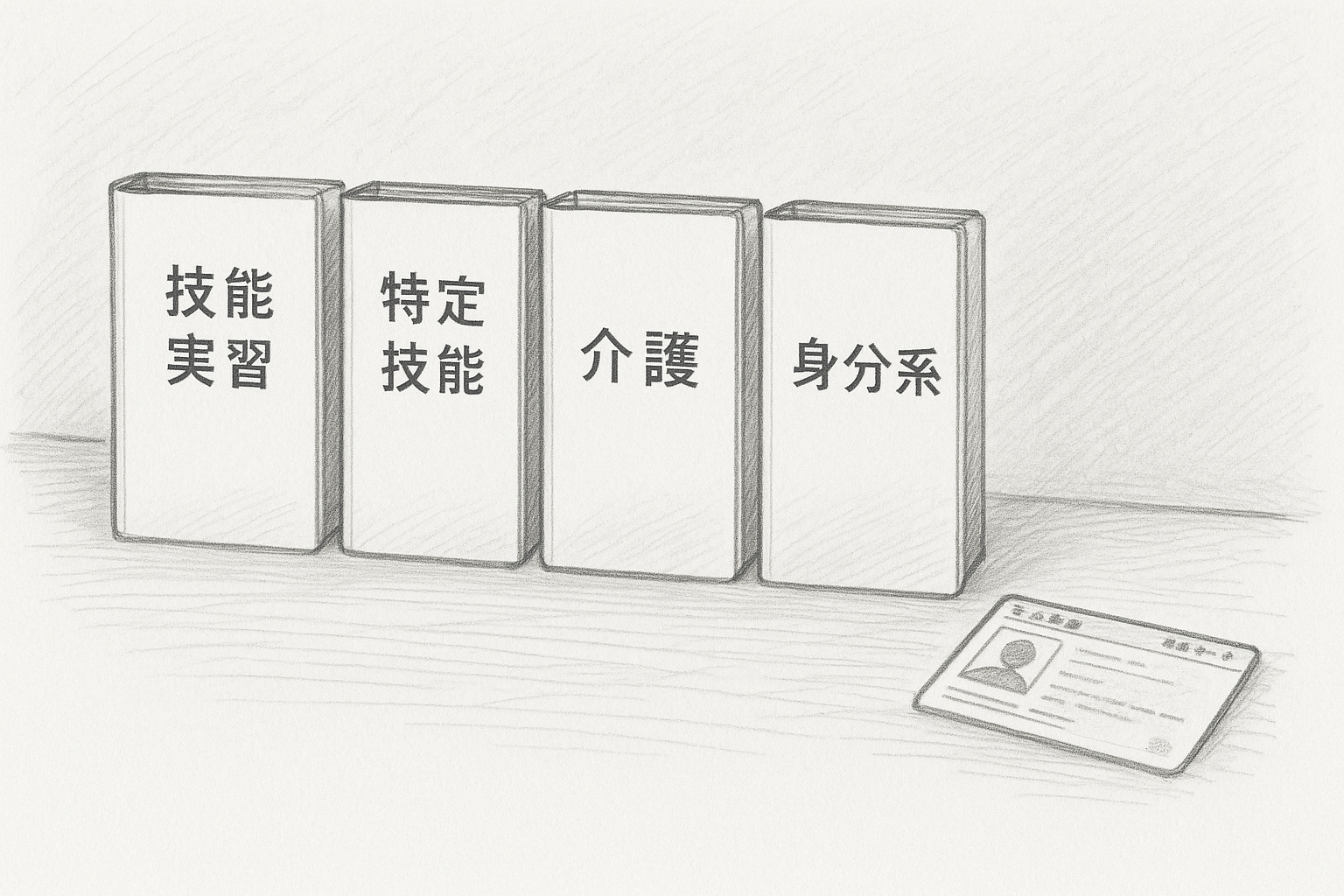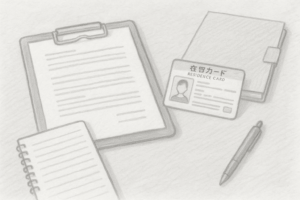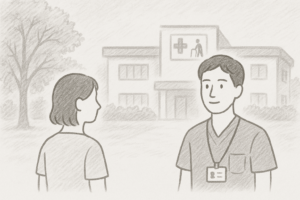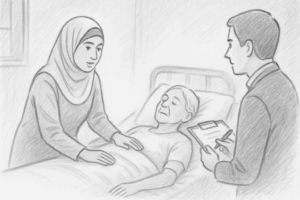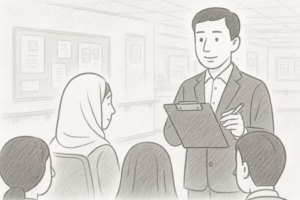外国人が日本の介護現場で働く場合、利用できる在留資格はいくつか存在します。代表的なのは、かつての技能実習、2024年6月の法改正で新設が決まり2027年までに施行予定の育成就労、そして現在の中核資格である特定技能「介護」、さらに介護福祉士国家資格を取得した後に得られる在留資格「介護」です。
加えて、日本人の配偶者や定住者、永住者といった「身分系」、さらには留学や家族滞在、特定活動といった資格から間接的に介護に関わる外国人も存在します。これらはそれぞれ目的や要件、在留期間、家族帯同の可否などが異なり、制度の趣旨もバラバラです。

この記事では、特定技能介護を中心に据えながら、他の在留資格と比較し、介護職の外国人が実際にどのようなキャリアルートを描けるのかを整理していきましょう。
技能実習 ― 介護が「後発」で追加された経緯
技能実習制度は「技能移転による人材育成」を名目に1993年から運用されてきましたが、介護職種が対象に加わったのは2017年と比較的遅い時期でした。他職種と比べて介護分野には特有の要件が課されました。
日本語要件の厳格さ
技能実習で介護職種に従事する外国人は、入国前から日本語能力試験(JLPT)N4相当以上が必須とされています。利用者とのコミュニケーションが不可欠であるため、他職種よりも言語要件が重視されているのです。
技能評価試験の導入
介護技能評価試験が設けられ、入国後もスキルを確認する仕組みが導入されました。これは介護特有の措置であり、実習生が一定の介護能力を持っていることを可視化する狙いがありました。
身体介助をめぐる議論
当初は「身体に直接触れる介助」を技能実習生が担ってよいのか議論がありました。安全性や利用者の尊厳を理由に制限も検討されましたが、最終的には可能とされ、実務上も広く担っています。



なるほど、他の分野より介護だけ日本語とか技能試験の条件が厳しかったのはそういう背景があったんですね。



そうです。介護分野は利用者の生命や生活に直結するため、他職種以上に制度設計で慎重に扱われてきたのです。
育成就労 ― 新制度での介護の位置づけ
2024年6月の改正入管法により創設が決まった育成就労は、公布から3年以内(=2027年6月まで)に施行予定です。技能実習の課題(人権侵害や転籍制限の厳しさなど)を是正し、より人材育成と就労を両立させることを目的としています。
介護分野における特徴(予定)
- 日本語力の重視:利用者の安全確保と生活支援を行うため、引き続きN4レベルが求められる見込み。
- キャリアパスの明確化:育成就労から特定技能介護へ移行できることが制度上も想定されている。
- 施設側の支援義務:生活支援や研修体制が特に強調されると見込まれ、厚労省の基準との二重規制的な側面も予想される。
育成就労は、修了後に技能測定試験と日本語試験に合格すれば特定技能「介護」へ移行できることが制度上想定されています。介護分野では、この「育成就労でスキルと日本語を身につけ → 特定技能「介護」に進む」という流れが、将来的に標準的なキャリアパスとして位置づけられる見込みです。



つまり育成就労は“準備段階”として設計されているんですね。ただ、まだ始まっていないんですね。



その通りです。今後の制度施行により、正式に利用可能となります。
特定技能介護 ― 制度の中核を担う資格
特定技能介護は2019年に創設された「特定技能」14分野のひとつで、慢性的な人手不足を補うことを直接の目的としています。
主な特徴
- 在留期間:最長5年(介護には2号が存在しないため、1号止まり)。
- 転職の可否:条件付きで転職可能。ただし同じ介護分野内での移動に限られます。
- 家族帯同:認められていません。介護分野は人材確保目的が強く、家族滞在は考慮されていないのが現状です。
- 国家試験への橋渡し:特定技能での実務経験が介護福祉士国家試験の受験資格につながるのが最大のポイント。
- 訪問系サービス解禁(2025年改正):2025年4月から、一定条件を満たせば訪問介護などの訪問系サービスにも従事可能となりました(厚労省通知2025/3/31)。



特定技能介護は“ゴール”ではなく、“介護福祉士へ進むためのステップ”です。ここで経験を積むことで、国家試験に挑戦できるようになります。
Case :フィリピン出身のDさん
Dさんは特定技能「介護」で来日し、5年間介護施設で働きました。その間に実務経験を積み、介護福祉士国家試験の受験資格を取得。4年目に合格し、在留資格を「介護」に切り替えました。介護ビザ取得後は更新制限もなく、家族も帯同可能となり、安定した生活基盤を築いています。



なるほど、特定技能はゴールではなく“中継点”なんですね。
介護ビザ(在留資格「介護」) ― ゴールとしての資格
在留資格「介護」は、介護福祉士国家試験に合格し、資格登録を済ませた外国人だけが取得できます。
特徴
- 在留期間:更新制限なし(1年・3年・5年ごとの更新)。
- 就労自由度:雇用先を変える自由があり、転職の制限もありません。
- 家族帯同:可能。
- 永住への道:在留要件を満たせば永住申請が可能で、特定技能に比べ圧倒的に安定性が高い。



介護ビザは“ゴール”です。ここまで来れば在留資格の更新制限もなく、永住も視野に入ります。
身分系・留学・家族滞在・特定活動 ― 制度外・周辺資格の関わり
ここまでは介護を本格的に担う“本道”の資格を見てきました。しかし実際の現場では、留学や家族滞在、特定活動といった資格を背景に、限定的ながら介護に関わる人材も存在します。これらは直接の就労資格ではないものの、将来の人材候補や補助的戦力として位置づけられるため、制度を理解するうえで欠かせない視点です。
身分系
身分系の在留資格とは、日本との身分関係や地位に基づいて与えられる資格です。介護に特化した制度ではありませんが、就労制限が一切なく自由に働けるため、介護現場でも重要な人材源となっています。
代表的なものは以下の通りです:
- 日本人の配偶者等(日本人の配偶者・実子など)
- 永住者の配偶者等
- 定住者(日系人やその家族など)
- 永住者(在留期間無期限)
これらの資格を持つ外国人は、試験合格や在留資格変更なしに介護分野で働けるのが大きな特徴です。施設側にとっても「支援計画」や「届出義務」がなく、雇用の自由度が高い一方で、制度による受け入れ枠とは区別して考える必要があります。



身分系は“制度に縛られない人材”です。介護人材不足の現場では貴重な存在であり、他の在留資格とは性格が大きく異なります。
留学
留学生は原則「学業専念」ですが、資格外活動許可を取れば週28時間までアルバイト可能です。介護施設で働く留学生も多く、将来特定技能や介護ビザへ移行する人材の“入口”として機能しています。
家族滞在
「留学生の扶養家族」や「就労資格者の家族」が対象。原則就労不可ですが、資格外活動許可を得ればアルバイトが可能です。本格的な就労には向きませんが、補助的労働力になることもあります。
特定活動
特定活動は告示や法務大臣の指定によって働ける活動が認められる在留資格です。介護分野ではEPA介護福祉士候補者が特定活動で来日し、国家試験合格後に在留資格介護へ移行するケースが典型です。
本格的な介護就労資格
| 在留資格 | 趣旨 | 日本語要件 | 在留期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 技能実習 | 技能移転による人材育成 | N4必須 | 最大5年 | 2017年追加、日本語必須、技能評価試験導入 |
| 育成就労(施行予定) | 人材育成+就労 | N4相当(予定) | 原則3年 | 2024年法改正で創設、2027年までに施行予定(現時点では未施行) |
| 特定技能「介護」 | 人手不足対応 | N4相当 | 最大5年(2号なし) | 国家試験受験資格に直結/訪問系サービス可(2025~) |
| 介護 | 国家資格保持者の就労 | 介護福祉士必須 | 更新制限なし | ゴール資格/永住直結/家族帯同可 |
周辺・補助的資格
| 在留資格 | 趣旨 | 就労可否 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 身分系 | 身分・地位に基づく | 就労自由 | 制度外だが自由度最大、永住直結可 |
| 留学 | 学業専念 | 資格外活動許可でアルバイト可(週28h、長期休暇40h) | 将来の介護人材候補として現場経験が可能 |
| 家族滞在 | 主たる資格に従属 | 資格外活動許可でアルバイト可(週28h) | 本格就労には不向き、補助的労働力 |
| 特定活動 | 個別指定 | ケースによる | EPA候補者→介護ビザへの中間段階など |
まとめと展望
介護分野における外国人の在留資格は、技能実習(将来は育成就労に移行予定)から特定技能介護を経て介護ビザに至る流れが「基本モデル」として制度設計されています。ただしこれは唯一の道ではありません。実際には、身分系や留学・家族滞在・特定活動といった周辺資格を通じて介護に関わる人材も存在し、キャリア形成は直線的な階段ではなく、多様な入口を持つ立体的なルートマップとして広がっています。
現時点では「技能実習→特定技能」という現行ルートが引き続き存続していますが、2027年までに育成就労が施行されれば、技能実習は廃止され、移行のための経過措置が設けられる見込みです。今後はこの新制度を前提としたキャリア形成が基本となるでしょう。
行政書士は、こうした制度全体の俯瞰と最新改正を踏まえて、最適な受け入れルートの選択から申請書類作成、届出対応まで一貫してサポートできます。結果的に、受け入れ後のトラブル防止や長期的な人材確保につながり、事業者に安心をもたらします。



現場に必要なのは「今ある制度」と「これからの制度」の両方を見通す視点です。
育成就労の施行と経過措置を踏まえた上で、どの在留資格が最適かを検討することが、安定した人材確保への第一歩になります。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)