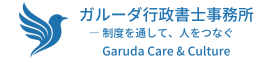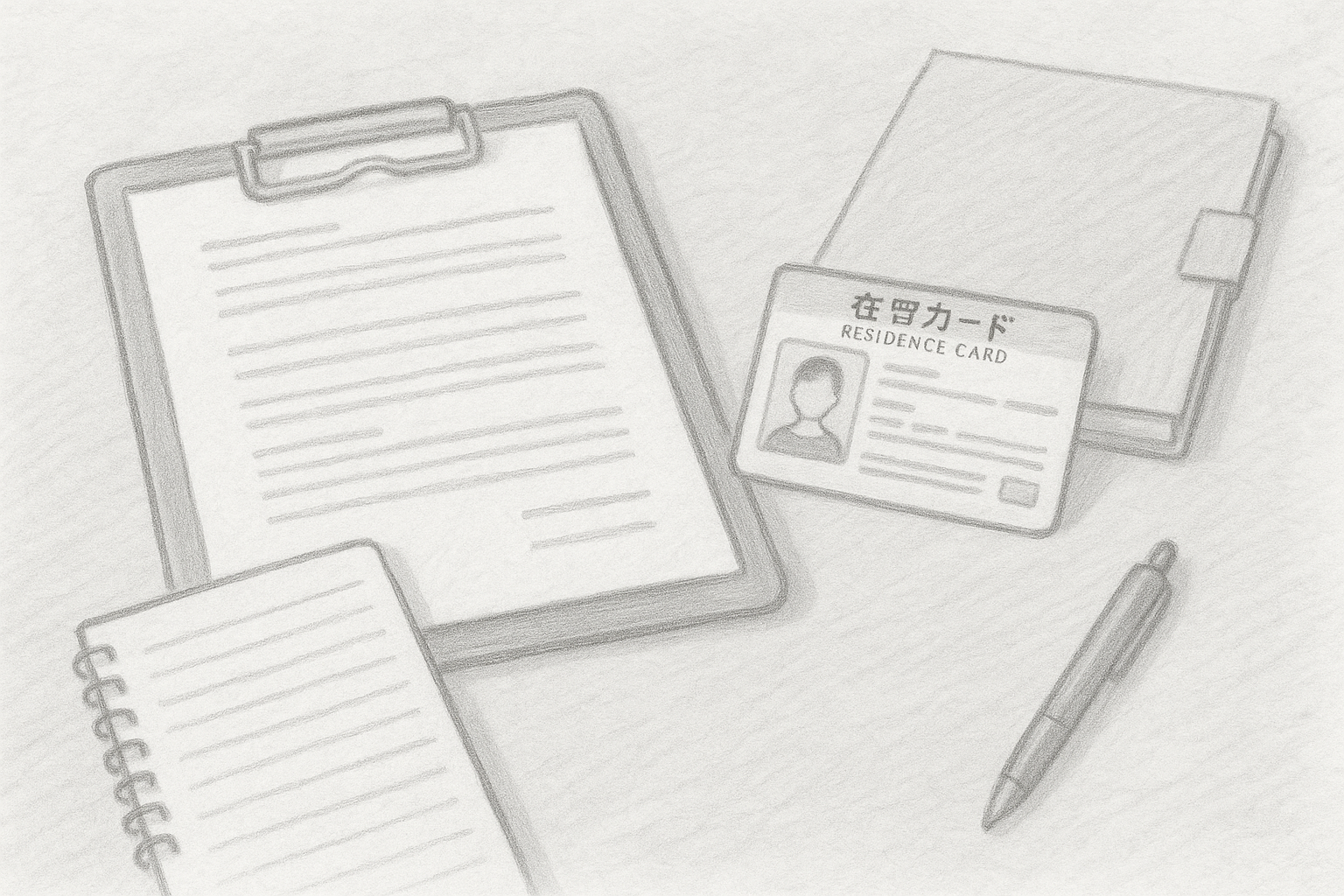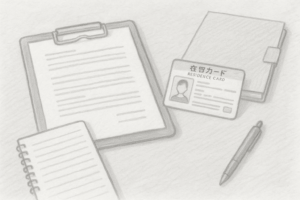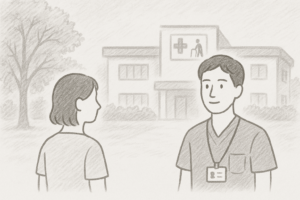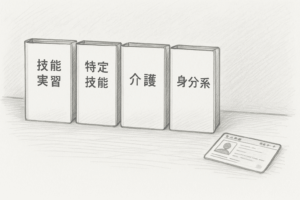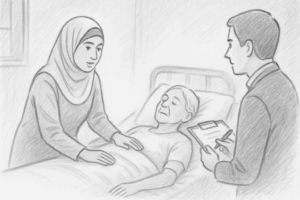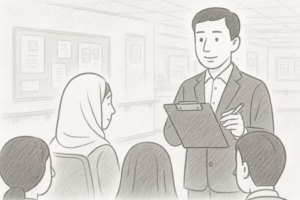※本記事は、2025年春以降に始まる「育成就労制度」への移行を前提にしています。
以下では、現行制度(2025年3月時点)の「技能実習」をもとに解説します。
新制度では「技能実習計画」が「育成就労計画」に置き換わるなど、一部の手続・用語が変更される予定です。
【出典:2025/3/11 閣議決定「特定技能・育成就労制度に関する基本方針」】
技能実習制度を動かすには、
「技能実習計画の認定」と「在留資格の許可」という二つの手続きを通らなければなりません。
どちらも時間と手間がかかる工程で、片方でも誤れば外国人を受け入れることはできません。
制度の仕組みを理解しておくと、
「監理団体に任せる部分」と「自社で整えるべき部分」を整理でき、
安全に制度をスタートさせることができます。
誰が何をするのか──誰が何をするのか──監理団体と施設を中心に
技能実習制度は、送り出し国・監理団体・受け入れ施設という三者の関係で成り立っています。
この基本構造は変わりませんが、
実際の運用で中心となるのは、日本側の監理団体と受け入れ施設です。
ここでは、その二者を軸に、実務上の役割を整理します。

監理団体にお願いすれば、申請も全部代わりにやってくれるんですよね?



監理団体は“代行者”ではなく、“支援と監督”の立場です。
書類づくりを手伝ってくれることはありますが、申請の責任主体はあくまで介護施設(実習実施者)です。。
監理団体は、書類の様式を整えたり、内容を確認したり、
OTIT(外国人技能実習機構)や送り出し機関との調整を行ったりします。
しかし、最終的に申請書へ署名・提出するのは受け入れ施設であり、
施設が制度上の「実習実施者」としてすべての責任を負います。
| 立場 | 主な役割 |
|---|---|
| 監理団体 | 書類の作成支援、様式確認、スケジュール調整、制度監督、送出機関との連絡調整(※法的代理ではない) |
| 施設(実習実施者) | 実習内容の設計、指導体制・雇用契約の整備、申請書への署名・提出(法的責任者) |
監理団体にすべてを任せきりにせず、
施設自身が“主語”となって制度を動かす意識が、
技能実習を成功させる第一歩です。
技能実習計画──制度の設計図
技能実習計画は、外国人が日本でどのように実習を行うかを定めた制度の設計図です。
この計画が認定されてはじめて、外国人を受け入れることができます。
実習の目的から教育体制、安全衛生、技能評価まで、すべてを具体的に示す必要があります。
申請主体は実習を受け入れる介護施設(=実習実施者)。
監理団体は計画書の作成を補助し、内容確認や提出の調整を担います。
技能実習計画に記載すべき主な項目
技能実習計画には、介護職種に特有の項目が数多く含まれます。
OTIT運用要領および厚生労働省のガイドラインに基づき、次の内容を具体的に記載します。
- 実習の目的・期間・段階(1号・2号・3号の別)
- 実習内容(身体介護、日常生活支援、介護記録の作成等)
- 指導体制(指導員・生活支援担当者の配置、指導方法)
- 教育計画(日本語教育、安全衛生教育、OJT・Off-JTの時間数)
- 評価方法(技能評価試験の受験時期・内容)
- 実習場所・勤務形態・勤務時間
- 実習生の生活支援体制(相談窓口・居住環境・地域交流)
介護職種では、実習の中心は身体介護等(入浴・食事・排せつなど)です。
利用者の心身の状況に応じた介助を計画的に学ぶことが求められます。
一方で、掃除や洗濯などの生活援助や単純作業だけでは「介護職種」とは認められません。
また、介護分野では実習生が直接人と関わる場面が多いため、
安全衛生・感染防止・倫理教育の記載も重視されます。
教育計画においては、OJT(職場内訓練)だけでなくOff-JT(講義形式の研修)の実施も必須です。
公的なモデル例の参照
厚生労働省の公式サイトでは、職種ごとの技能実習計画書モデル例が公表されています。
介護職種については、「外国人介護人材ポータルサイト」内に
記載例および留意事項をまとめたPDF資料が掲載されています。
このモデル例は、実際の審査基準に即して構成されており、
実習内容・教育計画・指導体制を作成する際の有効な参考資料となります。
技能実習計画の認定を受けるまで
技能実習計画は、作成しただけでは効力を持ちません。
外国人技能実習機構(OTIT)による認定を受けてはじめて有効になります。
認定の申請は、監理団体を経由してOTITに提出し、
OTITが内容を確認したうえで、法務省・厚生労働省と連携して審査します。
認定までには通常1〜2か月を要し、
内容が抽象的であったり、実施体制が不十分な場合は「補正指示」が出されます。
この補正が遅れると、その後の在留資格認定証明書交付申請も遅延します。
したがって、技能実習計画の段階から、教育・指導体制を具体的に整えておくことが重要です。



OTITの審査は形式より中身です。
「なぜこの期間でこの教育を行うのか」が説明できる計画であることが重視されます。
まず現場の教育スケジュールを固め、厚労省のモデル例と照らして文面を組み立てましょう。
技能実習の受け入れ準備──人と環境の整備
技能実習計画の作成と並行して、
受け入れ施設では実習体制と生活環境の整備を進める必要があります。
これらは計画の裏付けとして、OTIT(外国人技能実習機構)の審査でも重視される項目です。
技能実習責任者・指導員・生活指導員の選定
技能実習法第13条および施行規則第6条に基づき、
実習実施者は「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」を選任する義務があります。
- 技能実習責任者:実習全体の管理責任を負う。
実務経験5年以上、かつOTIT指定の「技能実習責任者講習」の修了が必要(同条第3項)。 - 技能実習指導員:現場で実習生を直接指導。
技能実習法施行規則第6条により、当該技能について5年以上の実務経験を有する者であることが求められます。
(介護分野では、介護福祉士等の資格を有し、実際に介護現場経験を積んだ職員が想定されます。) - 生活指導員:日常生活や地域適応を支援。
日本語での相談対応や地域生活サポートの体制を整えることが望ましい。
これらの担当者を事前に選任し、計画書にも氏名・役割を記載します。
形式的な配置ではなく、実際に指導・管理を行う人物を明示することが重要です。
宿舎・生活環境の整備
実習生が生活する宿舎も、OTITの確認対象です。
「適切な居住環境」を確保するため、以下の基準を参考に整備します。
- 1人あたりの居住スペース:概ね7㎡以上(法令上の義務ではなくOTITが示す適正運用上の基準)
- 施錠・換気・採光など安全衛生の基準を満たすこと
- トイレ・浴室・炊事設備を適切に共用または分離管理
- 消火器・避難経路・防災計画の整備(消防法・建築基準法等の一般法令に基づく)
- 通勤経路・地域生活支援(買い物・病院・公共交通機関)の確認
宿舎の賃貸契約名義は、原則として施設(実習実施者)または監理団体が負います。
実習生本人名義の契約はトラブルの原因になるため避けるのが基本です。
出典:OTIT『技能実習生の宿舎に関する適正運用ガイドライン(最新版)』
OTIT『技能実習制度運用要領(最新版)』
生活支援・通訳体制
外国人実習生にとって、生活支援は教育と同じくらい重要です。
特に介護分野では、文化的背景や言語の違いから離職につながる事例もあるため、
日本語サポート・相談窓口・地域交流の仕組みを整えておくと安心です。
- 母語サポート:監理団体または地域ボランティアとの連携
- 通訳対応:勤務初期の業務説明・安全教育での支援
- 定期面談:実習生と指導員の双方から課題を吸い上げる場を設ける



実習生の教育は“現場での仕事”だけではなく、
生活面の支援と安全配慮を含めた総合的な受け入れ計画として審査されます。
宿舎の契約や責任者講習など、申請直前に慌てることのないよう早めに準備をしましょう。
補足:OTIT審査の全体像──「書類」と「実態」の両面評価
技能実習計画は、単に形式が整っていれば認定されるわけではありません。
OTITの審査では、以下の3つのレイヤーから計画の実現性が総合的に判断されます。
| レイヤー | 内容 | 関連する提出書類・準備項目 | 主な確認主体 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 体制の整備 | 実習を安全に実施できる組織体制の有無 | 技能実習責任者・指導員・生活指導員の選任書、講習修了証、組織図 | 実習実施者(施設)+監理団体 |
| Ⅱ. 教育・安全衛生の計画 | 実習内容の具体性と教育の実現可能性 | 技能実習計画書、指導スケジュール、技能評価試験計画、安全衛生教育計画 | OTIT(技能実習計画の認定) |
| Ⅲ. 生活環境・支援体制 | 宿舎・生活支援・相談窓口などの生活面の整備 | 宿舎図面・契約書・生活指導マニュアル・母語支援体制書 | OTIT+監理団体 |
OTITは提出書類をもとに審査するだけでなく、
必要に応じて施設担当者へのヒアリングや現地確認を行います。
したがって、紙面上の計画だけでなく、
実際に「その通りに動かせる現場体制」が整っていることが重要です。
在留資格認定証明書の申請──入管での審査
技能実習計画がOTITで認定されると、
次は出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請主体は受け入れ施設ですが、
実務では監理団体が資料を取りまとめて提出する形が一般的です。
入管で確認される主なポイントは次の三つです。
- 雇用契約が実態を伴っているか
- 実習計画と契約内容が一致しているか
- 監理団体との関係が適正か



監理団体が入管に提出するって聞きましたけど、正式な代理人なんですか?



“代理人”というより、“申請取次者”という制度があるんです。
入管に正式に書類を出せるのは、原則として本人、または届出済みの行政書士・弁護士です。
監理団体は補助として書類を整えることが多いですが、
公益法人などで地方入管から承認を受けた場合には、例外的に取次が認められるケースもあります。
申請が受理されると、通常1〜2か月で「在留資格認定証明書」が交付されます。
ただし、審査期間は申請の内容・時期・入管局の混雑状況によって変動します。
介護分野では、次のような点が審査で確認されます。
- 雇用契約の実在性:給与水準・勤務時間・社会保険の加入状況が、国内労働者と同等であるか。
- 教育体制の整合性:OTITで認定された技能実習計画と契約書・指導体制が一致しているか。
- 監理団体の適正性:過去の指導歴や監査結果に問題がないか。
提出書類の不備や照会対応の遅れがあると、1〜2か月では済まないこともあります。
とくに、OTIT認定後の補正が入管審査中に発覚すると、いったん差戻し扱いとなり、再審査に入る場合もあります。



交付まで1〜2か月」はあくまで順調に進んだ場合の目安です。
実際には、施設側と監理団体の間で補正資料をやりとりする期間が含まれるため、
スケジュール上は“3か月程度の余裕”を見ておくと安全です。
入管からの電話照会や追加書類要請は突然来ることがあります。
あらかじめ担当者を決め、連絡体制を整えておくと慌てずに対応できます。
入国までの流れとスケジュール管理
在留資格認定証明書が交付されたら、いよいよ渡航準備の最終段階に入ります。
この時期のスケジュール管理は、制度全体の中でも最も神経を使う場面です。
① 査証申請(在外公館)
交付された在留資格認定証明書をもとに、送り出し国の在外公館(日本大使館・領事館)で査証(ビザ)の発給を申請します。
申請者は原則として実習生本人ですが、実務上は現地送出機関が代行して窓口対応を行います。
審査には通常1〜2週間を要し、書類の不備や照会があるとさらに時間が延びることもあります。
② 渡航前オリエンテーション
出発前に、現地の送出機関が日本語・生活ルール・安全衛生などの研修を実施します。
これは制度上義務付けられた教育であり、修了証が発行されます。
OTITの確認対象でもあるため、施設は研修実施日と内容を把握しておくと安心です。
③ 渡航と入国審査
入国時には、空港で在留カードが交付されます。
在留資格は「技能実習(1号)」、在留期間は原則1年。
入国の時点で在留資格が確定するため、この日までは一切の就労行為をしてはいけません。
これは“資格外活動”と見なされ、たとえ見学や短時間の手伝いであっても問題となる場合があります。
④ 入国後講習の準備(監理団体)
入国直後から1か月程度、監理団体による講習期間が設けられます。
この期間中、実習生はまだ配属先で働くことはできません。
施設は、配属予定日から逆算して雇用契約やシフト計画を立てる必要があります。
(※講習と配属の具体的な流れは、次回記事で詳しく扱います。)



スケジュール管理で最も多い誤りは「在留資格が下りる前に準備を進めすぎる」ことです。
実際の労働開始日は入国・講習修了後。
雇用契約書の日付や給与支給開始日を早く設定しすぎると、
審査で“在留資格と実態の不一致”と指摘されることがあります。
安全策としては、入国予定日+講習期間を考慮した日付設定が望ましいです。
まとめ──制度を正しく動かす力を持つ
技能実習制度の信頼は、ひとつひとつの手続の正確さに支えられています。
監理団体は制度を支えるパートナーであり、
そして介護施設自身が制度を正しく動かす“主語”です。
制度を形だけで終わらせず、
計画づくりから申請、入国準備までの手順を丁寧に積み重ねることが、
実習生にとっても安心できる受け入れ環境を生みます。
制度の理解はゴールではなく、次の段階の準備です。
次回は、入国後の講習と現場体制づくりを中心に、
実習を“動かす”フェーズを見ていきます。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)