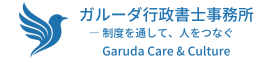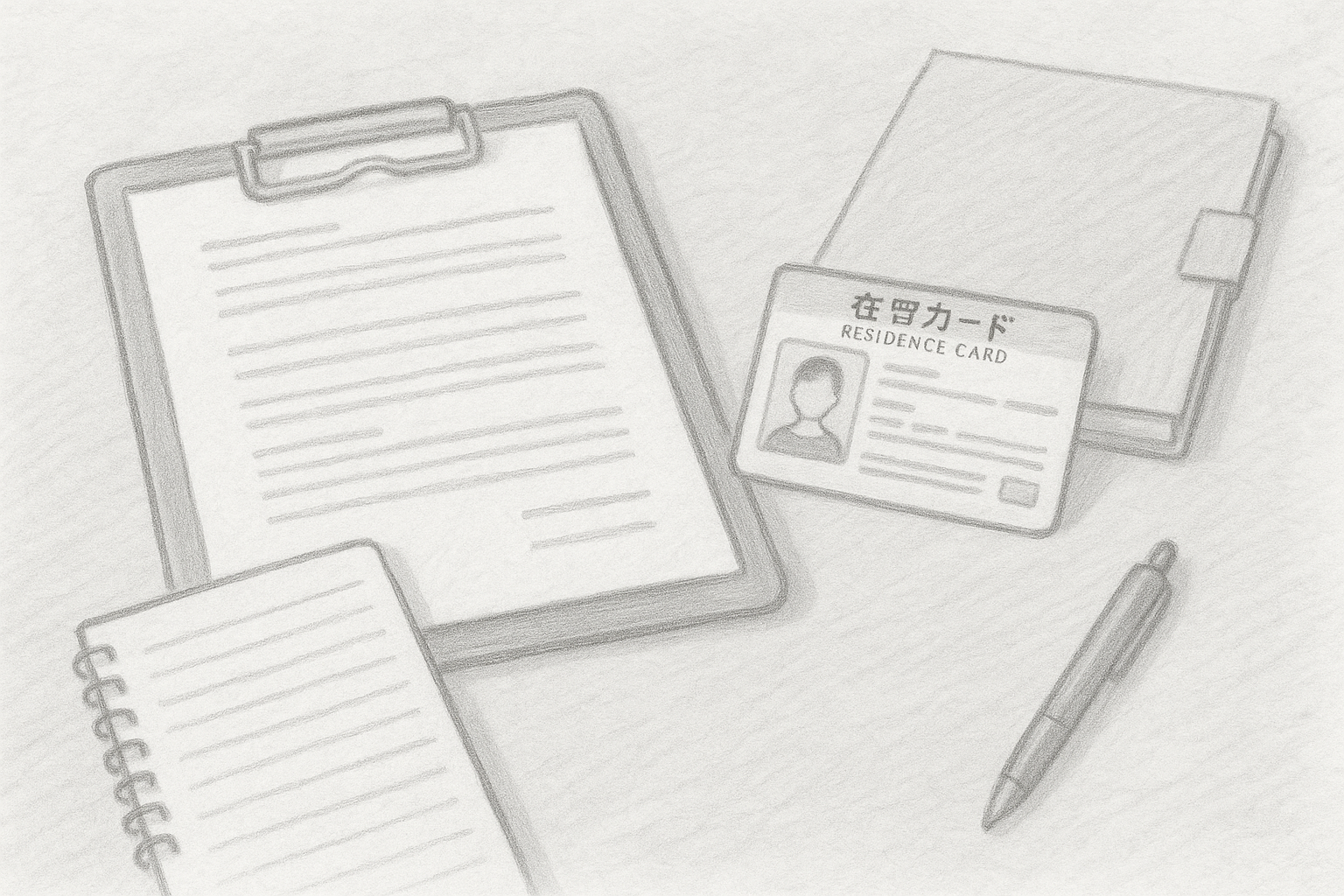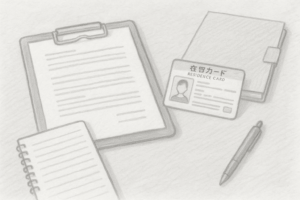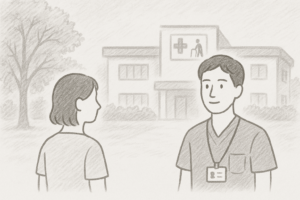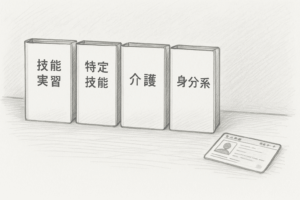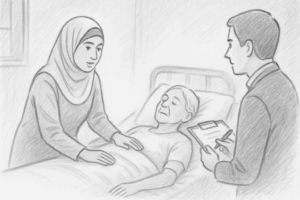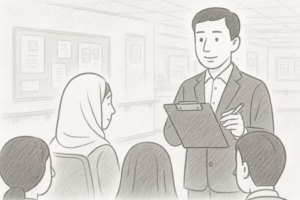※本記事は、2025年春以降に始まる「育成就労制度」への移行を前提にしています。
以下では、現行制度(2025年3月時点)の「技能実習」をもとに解説します。
新制度では「技能実習計画」が「育成就労計画」に置き換わるなど、一部の手続・用語が変更される予定です。
【出典:2025/3/11 閣議決定「特定技能・育成就労制度に関する基本方針」】
介護施設が外国人技能実習生を受け入れる際、最初の関門となるのが「採用」と「監理団体との契約」です。
人手不足を背景に制度導入を検討する施設は増えていますが、仕組みを理解しないまま進めると、思わぬ行き詰まりを招くことがあります。

外国人を採用したいんですが、何から始めればいいのか見当がつかなくて……



まず、“どの制度を使うか”を決めましょう。技能実習には人数や期間の制限があり、段取りを誤ると動けなくなります。
制度を選ぶというのは、単に「どの在留資格で採用するか」を決めることではありません。
それぞれの制度には、受け入れの目的・期間・関与する機関が異なる仕組みがあります。
なかでも技能実習制度は、国際的な人材育成を目的とした“教育型の制度”として設計されており、
採用手続も、一般的な雇用契約とはまったく異なる流れをたどります。
まずは、この制度がどのような枠組みで成り立ち、
誰がどの部分を担っているのか――
その「制度の骨格」を理解するところから始めましょう。
技能実習制度の骨格──三者関係と監督体制のしくみ
技能実習制度は、送り出し国・監理団体・受け入れ施設という三者の関係で成り立っています。
法的には、監理団体が技能実習生の適正な実施を監督する義務を負い(技能実習法第23条〜第28条)、送出機関は二国間取決めに基づき人材を派遣します。
この三者の関係を正しく理解することが、制度を動かす第一歩です。
さらに、この三者の関係の上位には、制度全体を監督する公的機関が存在します。
外国人技能実習機構(OTIT)は、技能実習法に基づいて設立された中核機関で、
監理団体や実習実施者(介護施設など)の適正な運用を確認し、
実習生の人権保護や教育内容の質を担保する役割を担っています。
法務省(出入国在留管理庁)は、在留資格の許可や在留期間の管理を行い、
厚生労働省は職種・作業の告示や安全衛生、労働条件の監督を担当します。
この三つの機関が連携することで、制度の法的・運用的な均衡が保たれています。
介護分野では特に、
・OTITによる技能実習計画認定の確認
・入管による在留資格審査
・厚労省による職種要件・教育カリキュラムの告示
が一体的に運用されています。
つまり、制度は監理団体と施設だけで完結するものではなく、
行政機関が上位で見守る“公的枠組み”の中で動いています。
この構造を理解しておくと、
制度を単なる雇用スキームではなく、「国際的な教育制度」として正しく位置づけられるでしょう。
[上位監督]
法務省(入管) ─ 厚生労働省 ─ 外国人技能実習機構(OTIT)
│(在留管理・職種告示・監督)
↓
[中間運用]
監理団体 ─ 送出機関(海外)
│(実習生募集・教育・監督)
↓
[現場実施]
介護施設(実習実施者)
│(実習指導・雇用・支援)
↓
[実習生]
外国人技能実習生
対象職種と受け入れ条件
介護分野で技能実習の対象となるのは「施設介護職」が基本です。
長らく訪問介護やデイサービスなど、利用者宅での支援は制度の対象外とされてきました。
これは、利用者宅では安全管理や指導監督が難しいためです。
しかし、2025年4月1日施行の厚生労働省告示第320号により、制度の一部が改正されました。
介護職員初任者研修を修了し、1年以上の実務経験を有する技能実習生は、
一定の条件下で訪問系サービス(生活援助を除く)に従事できるようになっています。
受入事業所には、同行訓練・利用者説明・安全確保措置などの追加的義務が課され、
監理団体も教育計画・監督体制を強化する必要があります。



以前は“訪問は不可”でしたが、2025年4月以降は要件付きで可能になりました。ただし、準備と体制づくりが整っていないと認定が遅れる可能性もあります。
技能実習生を受け入れることができるのは、介護保険法に基づく指定事業者や、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの介護施設です。
これらの施設が制度上の受け入れ主体となります。
また、施設自身が3年以上の運営実績を持ち、労働保険・社会保険に適正に加入していることが求められます(OTIT「介護職種に係る技能実習運用要領」2024年3月改訂 p.8)。
これらの条件は、事業の継続性と職員体制の安定性を確保するためのものです。
実習は短期雇用ではなく、数年にわたる計画的な受け入れを前提としているため、
受け入れ施設には、実習生を支援しながら育てられる環境づくりが求められます。
協定国と送出機関の仕組み
技能実習は、原則として送り出し国との二国間協定(政府間の協力覚書)に基づいて実施されます。
この協定に基づき、相手国政府が認定した送出機関が人材を派遣し、日本側の監理団体と連携して運用されます。
現在、主要な送り出し国(ベトナム・インドネシア・フィリピン・ミャンマーなど)はすべて協定締結済みであり、
介護分野ではこの協定ルート以外の受け入れは制度上想定されていません。
2024年7月時点で協定を結ぶ国は16か国にのぼり、政府は引き続き受け入れ対象国の拡大を検討しています(関係閣僚会議決定 別紙一覧 2024/5/24)。
受け入れ施設が直接海外で採用活動を行うことはできません。
現地の送出機関が候補者を募集・教育し、監理団体を通じて日本側の施設とマッチングを行います。



直接採用できたら早いのにと思うんですが……



そう感じる施設さんは多いです。けれど、実習生の採用は生活や家族を背負った“海外就労”でもあります。
その過程でトラブルや不正が起きないようにするために、国同士でルールを決めて、間に公的な監理団体を置く仕組みが作られたんです。
日本と送り出し国の双方で審査や講習を重ねるこの手続きは、手間に見えて、“信頼の担保”そのものです。
この国際的な積み重ねがあってはじめて、制度が安心して続けられるようになっています。
受け入れ人数の上限
技能実習では、施設規模に応じて受け入れ人数の上限が決められています。
たとえば常勤介護職員が20人の施設であれば、最大5人までが上限です。
この上限は「教育負担を考慮した適正規模」を保つために設けられています(OTIT運用要領 p.16)。
| 常勤介護職員数 | 受け入れ上限人数 |
|---|---|
| 5〜10人未満 | 1人 |
| 10〜20人未満 | 2人 |
| 20〜30人未満 | 3人 |
| 30人以上 | 常勤介護職員数の20%(小数点切り捨て) |
初めての受け入れでは、制度運用を学ぶためにも少人数から始めるのが現実的です。
採用スケジュールの全体像
採用から入国までの期間は、通常6〜9か月程度です。
この間に、監理団体・送出機関・入管それぞれの手続が連動します。
- 監理団体の選定と契約
- 送出機関の選定(監理団体を通じて実施)
- 現地またはオンラインでの面接・採用決定
- 技能実習計画の認定申請(地方出入国在留管理局長経由でOTIT確認を経て、法務大臣が認定)
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証発給 → 入国・入国後講習 → 配属



半年で採用できると思っていましたが、想像以上に長いですね。



審査が多い分、安全に進められる仕組みです。
手続きを滞りなく進めるには、監理団体を中心に、送出機関や行政書士など関係者が情報を共有しながら準備を進めることが重要ですよ。
採用は“雇う”というより、“制度を動かす”段階です。
ここを丁寧に設計しておくことで、後の在留管理やトラブル対応が格段にスムーズになります。
ケーススタディ:初めて技能実習生を採用した施設
地方の特別養護老人ホームAは、慢性的な人手不足に悩んでいました。
新卒採用はここ数年ほとんどゼロ、パート職員も定着しない。
そんな中、監理団体から「技能実習生の受け入れ」を提案され、慎重に検討を始めました。



正直、外国人の方に介護をお願いするなんて、うちにできるのか不安でした。
A施設はまず、監理団体を通じてベトナムの送出機関と面談を実施。
候補者3名は全員、現地で日本語教育を受け、介護の基礎講習も修了していました。
面接では、笑顔で「日本で介護を学びたい」と話す姿が印象的だったといいます。
採用を決めてからは、「技能実習計画の認定申請」が最初の壁になりました。
教育計画や就業規則、指導員の配置記録など、提出書類は膨大。
特に「OJT(職場内訓練)」の計画づくりでは、
現場のスケジュールと教育時間のバランスに苦労しました。



書類を作るだけではなく、“現場で何を教えるか”を整理する作業になります。そこが制度の肝なんです。
最初の申請では、教育内容が抽象的だとしてOTITから補正を受けました。
「毎月の指導計画をもう少し具体的に」との指摘。
再提出に1か月を要しましたが、最終的に無事認定が下り、3名の実習生が入国しました。
入国直後は、言葉の壁がやはり大きかったそうです。
記録の書き方や利用者との会話で、誤解が生じることもありました。
しかし、「指導員の日報」と「実習生のふりかえりノート」を共有する仕組みを作ったことで、
次第に意思疎通がスムーズに。
3か月を過ぎる頃には、実習生の一人が夜勤前の申し送りを日本語で行うようになり、
周囲の職員が拍手で迎えたというエピソードも。



文化も言葉も違うけど、“同じ利用者を支える仲間”という感覚が芽生えました。初めての受け入れは不安も多かったけれど、
いまは「やってよかった」と感じています。
監理団体との契約──制度を支えるもう一つの柱
監理団体との契約は、技能実習制度の根幹に関わります。
介護施設は技能実習法第24条に基づき、監理団体の監督を受ける立場です。
監理団体との契約時に確認すべきポイントは以下の通りです。
- 監理費用の内訳(監査費・報告費・講習費など)
- 報告・監査の頻度と方法
- 送出機関との連携体制
- トラブル発生時の対応手順
2023年度以降、OTITは監理団体への監査において、
監理費用の内訳(実費・明細開示)や費用説明の透明性を重点的に確認しています。
これは法改正による義務ではありませんが、
実務上の監査ポイントとして扱われており、施設側も費用構造を理解して契約することが重要です。



監理団体は“監督者”でもあり、“伴走者”でもあります。内容を理解しないまま任せると、施設も制度の歯車になってしまいますよ。
まとめ:採用段階で整える「制度対応の基礎体制」
技能実習制度は、監理団体・送出機関・受け入れ施設がそれぞれの役割を担う複雑な仕組みです。
手続きは多岐にわたり、関係者も多いため、最初に制度全体を整理しておかないと、
「何を、いつ、誰が行うのか」が見えづらくなります。
さらに、監理団体は制度の適正運用を監督する立場にあるため、
施設側が独自判断で動くには限界があります。
「制度を理解しておかないと、言われるままに進んでしまうのでは」と不安を感じる方も少なくありません。
そんなとき、行政書士は制度の“通訳”としての役割を果たします。
受け入れの初期段階から関わり、
・受け入れ人数や要件の確認
・契約内容のチェック
・教育計画や申請書類の整備
といった部分を一緒に整理することができます。
監理団体が制度の運用を担う一方で、
行政書士は施設が制度を「安全に、無理なく」動かせるよう支える立場です。
複雑な制度を地図のように整理し、判断の根拠を示しながら進めていく──
それが、現場に寄り添う専門家としての行政書士の役割です。
次回は、実際の技能実習計画の立て方と、入管手続の流れを詳しく見ていきます。
制度の“設計図”をどのように描き、どんな書類を整えていくのか──
受け入れの具体的なステップを、実務の視点から整理します。
注記:本稿は2024年7月時点の公表資料(法務省・厚労省・OTIT)に基づき執筆。
2025年4月1日施行の厚生労働省告示第320号により、技能実習生による訪問系介護業務(生活援助を除く)が条件付きで可能となっています。
技能実習制度全体は2027年度までに「育成就労制度」へ移行予定(関係閣僚会議決定 2024/5/24)。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)