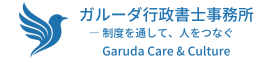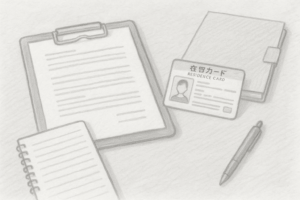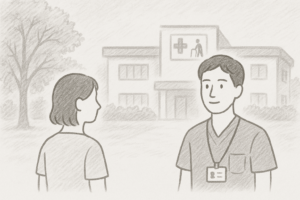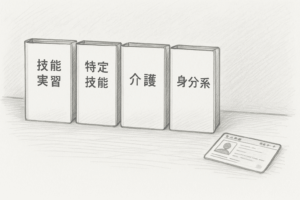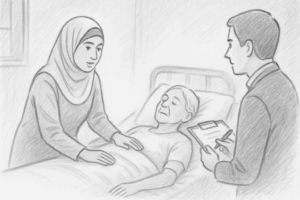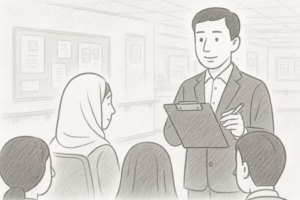特定技能制度は現在16分野に広がっています。その中でも「介護」は最も独自色の強い分野です。他分野では日本語試験はN4程度で足りますが、介護では介護日本語評価試験が追加されます。これは「人命や安全に直結する業務」である介護ならではの措置です。

介護分野は、一般日本語+介護日本語の二重構造が必須です。建設や外食では日常日本語だけでよいのに、介護だけ例外なんですよ。



やっぱり介護は人と人との距離が近い分、正確なコミュニケーションが命なんですね。
日本語能力要件 ― 一般日本語+介護日本語
特定技能「介護」では、一般的な日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)に加えて、「介護日本語評価試験」の合格が必須です。これは介護現場で必要となる専門的な日本語力を確認するための試験です。
JLPT N4は、世界各地の試験会場で年2回(7月・12月)実施されています。日本に来る前に受験できるのは利点ですが、年2回に限られるため、受験のチャンスが限られている点に注意が必要です。
一方、JFT-Basicはパソコン受験で、原則として毎月実施されます。海外会場も多数設けられており、計画的に挑戦しやすい柔軟性が特徴です。受験機会の多さから、渡日前に合格を目指す候補者にとって利用しやすい試験となっています。
JLPTとJFT-Basicの実施国・地域(代表例)
| 地域 | JLPT(日本語能力試験) | JFT-Basic(日本語基礎テスト) |
|---|---|---|
| 東南アジア | インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー など | フィリピン、カンボジア、インドネシア、ネパール、モンゴル、ミャンマー、タイ など |
| 南アジア | インド、スリランカ、バングラデシュ、ネパール など | インド、バングラデシュ、ネパール |
| 東アジア | 中国、韓国、モンゴル、香港、台湾 など | モンゴル |
| 日本国内 | 全都道府県主要都市 | 日本国内(Prometric会場) |
介護日本語評価試験は実際に現場で働くために必要な「介護特有の日本語力」を確認する試験です、次のような場面を想定した問題が出ます。
- 「体を横に向けてください」「おかゆは食べやすいですか?」といった声かけ表現
- 「バイタルサイン」「嚥下障害」といった専門用語
- 介護記録に必要な短文記述
- 実施方法:CBT方式(コンピュータ試験)。専用会場に設置されたPCで受験します。
- 試験時間:約30分
- 問題数:15問(介護用語・声かけ・記録の3分野 × 各5問)
- 実施場所:日本国内のCBT試験会場、及びベトナム・インドネシア・ネパールなど主要な送り出し国でも実施
- 合否通知:試験後すぐに画面で仮結果が表示され、5営業日以内に公式サイトで正式発表
- 再受験制限:不合格の場合、45日間は再受験できません



つまり、N4やJFTで“生活日本語”を担保し、介護日本語評価試験で“仕事に必要な日本語”を担保する。二重のハードルを設けて安全性を確保しているんです。



利用者さんとの会話や記録は、試験の合否以上に現場で直結する部分ですね。
技能実習からの移行 ― 試験免除
技能実習2号を「良好に修了」した外国人は、同じ分野の特定技能1号へ移行する際、原則として技能試験と日本語試験が免除されます。これは、技能実習が「一定期間の現場就労を通じて技能を習得した」とみなされる制度設計のためです。
介護分野の試験免除ルール
介護については特別なルールがあります。
- 一般日本語試験(JLPT N4/JFT-Basic) → 免除
- 介護技能評価試験 → 免除
- 介護日本語評価試験 → 免除
- 一般日本語試験(JLPT N4/JFT-Basic) → 免除
- 介護技能評価試験 → 受験必要
- 介護日本語評価試験 → 受験必要
訪問系サービス ― 条件付きで解禁と日本語の壁
2025年4月の改正で、訪問系サービスにも特定技能「介護」が従事できるようになりました。
訪問系特有の難しさは日本語コミュニケーションの負担が格段に大きい点にあります。
施設介護では周囲に同僚がいるため、誤解が生じてもフォローできます。しかし訪問介護では一人で利用者宅に入るため、利用者や家族との会話を正確に理解し、その場で対応する力が不可欠です。特に高齢者特有の言い回しや方言を聞き取るのは、日本語試験に合格していても難しいことがあります。さらに、訪問直後に記録を残す必要があるため、短時間で的確に日本語でまとめる文章力も求められます。



訪問介護は制度上解禁されましたが、日本語の壁は施設以上に大きいです。誤解の余地を減らす日本語力がなければ、事故や不信につながりかねません。



確かに施設なら周りに確認できますけど、訪問は一人で判断しなきゃいけない。日本語力が足りないとリスクが大きいですね。



訪問系で配置するなら試験合格だけでは不十分です。方言への対応訓練や、家族への説明ロールプレイなど、追加研修を取り入れることが望ましいですね。
Case:訪問介護事業所での導入
ある訪問介護事業所では、外国人職員を導入するにあたり、マニュアルを英語とベトナム語に翻訳するだけでなく、利用者や家族との会話を想定した日本語研修を徹底しました。「方言対応リスト」を作成し、同行訪問中に逐一確認しながら慣れていく仕組みを整備したところ、利用者家族から「安心して任せられる」と評価されました。制度改正だけでなく、現場で求められる日本語力をどう補うかが成功の鍵だった事例です。
試験合格後に立ちはだかる日本語の壁
JLPTやJFT-Basic、介護日本語評価試験に合格しても、実際の介護現場で求められる日本語はさらに高度です。
- カンファレンス:医師や看護師と速いテンポで専門用語を使った議論
- 記録:略語や専門用語を使いながら正確に書き残すスキル
- 家族対応:敬語や配慮を交えた説明力
日本語に関していえば、試験はあくまで入り口にすぎません。現場で必要となるのは、試験で測れる範囲を超えた日常会話力や家族対応の表現力です。合格後にどのような日本語支援や研修を組み込むかが、外国人職員が長期的に定着できるかどうかの分かれ道になります。
もっとも、こうした支援をすべて事業所が自前で担う必要はありません。登録支援機関に日本語学習を委託したり、地域の日本語学校や研修機関と連携したりすることで、外部の専門サポートを活用できます。
Case:日本語支援の有無で分かれた結果
ある介護施設では、外国人職員向けに週1回の日本語授業を導入しました。授業では単に文法や単語を教えるのではなく、実際の家族対応を想定したロールプレイを繰り返しました。例えば「お父さまの食欲が落ちてきています」「服薬の時間が少しずれました」といった、現場でよくある説明を練習させたのです。その結果、外国人職員は家族に対して堂々と状況を説明できるようになり、信頼を得たことで自信も高まりました。数か月後には離職率が大幅に低下し、定着につながりました。
一方で、別の施設では特別な支援を設けず、現場任せにしていました。外国人職員は介助自体は問題なくこなせても、記録業務や家族への報告で言葉に詰まり、叱責を受ける場面が増加しました。「ちゃんと伝わらない」「間違ったらどうしよう」という不安から職員は疲弊し、結局短期間で帰国してしまうケースが相次ぎました。現場の“あるある”ですが、日本語力の支援があるかないかで職員の定着度が大きく分かれることが浮き彫りになった事例です。
現場のチェックポイント
試験と日本語要件は、単に「受かればいい」ものではありません。採用計画や体制次第で、申請のスムーズさや定着率に直結します。
- 候補者がどの試験をいつ受験するのか把握しているか
- 施設内で試験対策や支援体制をどう設けるか(外部の日本語教育機関を含む)
- 実習生から移行する場合、免除規定を正しく活用しているか
- 訪問系サービスに従事させる際、体制要件を満たしているか
- 採用後も日本語研修やOJTを継続する計画を持っているか
これらは「在留資格が下りるか」「現場に定着するか」という成否に直結します。特に試験日程や訪問系の体制要件は専門的判断が必要で、行政書士や教育機関と早期に連携することがリスク低減につながります。
まとめ
特定技能「介護」は、他分野と比べても日本語要件において際立った独自性を持っています。一般的な生活日本語を確認するJLPT N4やJFT-Basicに加えて、介護の現場で実際に使う専門表現や声かけを測る介護日本語評価試験まで求められるのは介護だけです。
こうした二重の仕組みは単なるハードルではなく、日本社会が直面する高齢化と人材不足に対応するための制度設計です。介護は利用者の命や生活に直結する仕事であり、誤解のないコミュニケーションが安全性と信頼性を支えます。厚労省や入管庁が「介護だけ特別に日本語を重視」するのは、まさにこの現場特性を踏まえたものです。



特定技能『介護』の日本語要件は、“外国人を受け入れるための試験”ではなく、“質を守りながら受け入れるための仕組み”です。
試験に合格しても方言や家族対応の敬語までは十分にカバーできません。だからこそ、登録支援機関や教育機関と連携し、継続的に研修や支援を組み込むことが大切です。
試験で基礎を確認し、その後の研修で実務的な日本語を積み上げる。これが制度の意図するところであり、事業者にとっても外国人職員にとっても、そして利用者とその家族にとっても安心につながる仕組みです。特定技能「介護」の日本語要件を正しく理解し、受け入れ体制に反映させることが、今後の人材確保と定着を左右する大きな鍵になるのです。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)