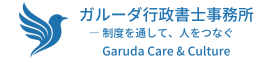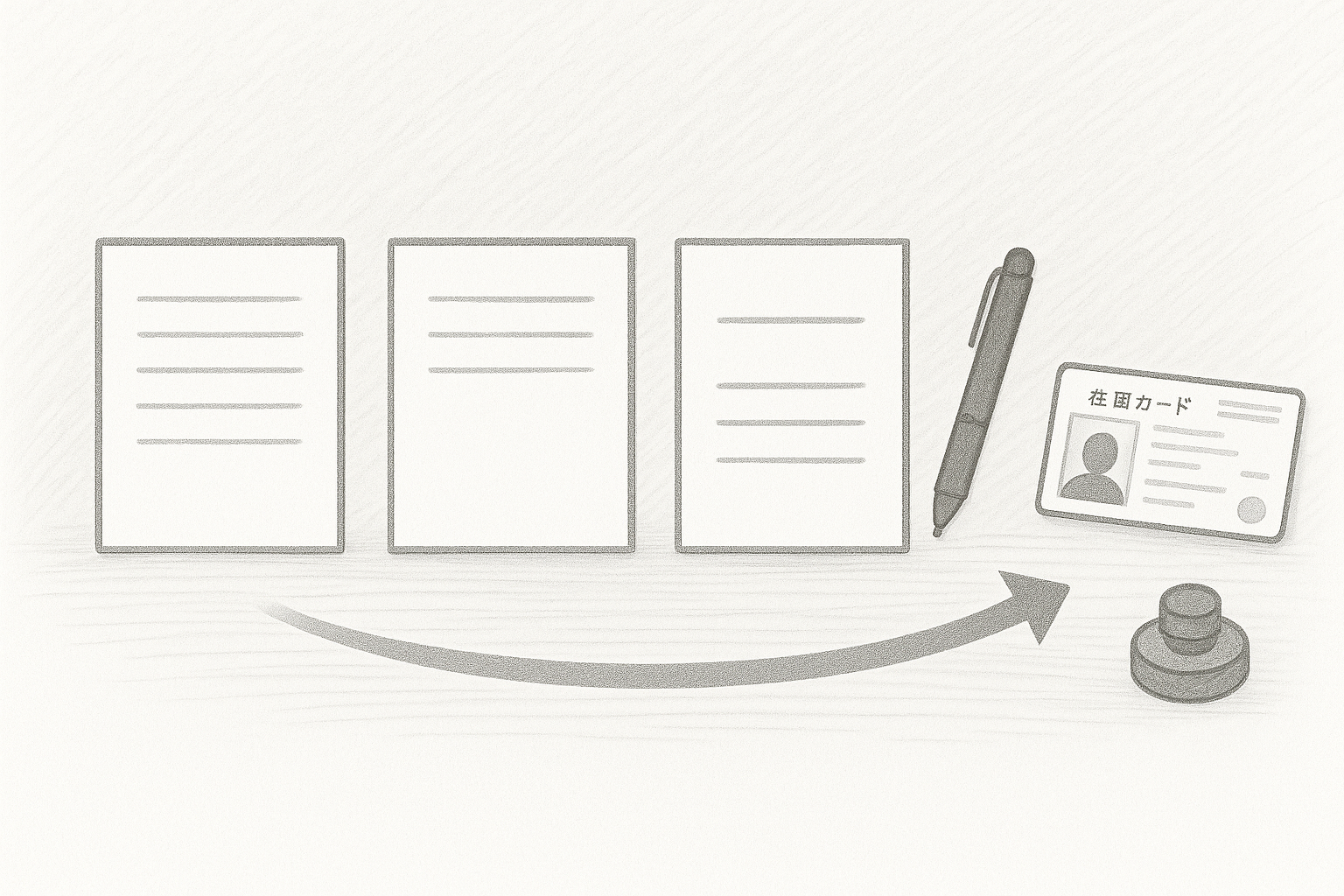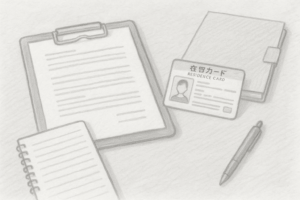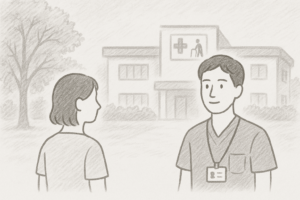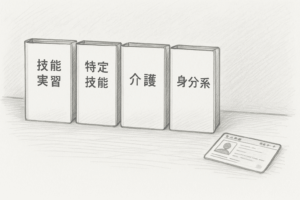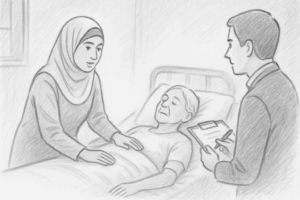定期届出
特定技能介護で外国人を採用している所属機関が必ず対応しなければならないのが「届出」です。届出は単なる事務作業ではなく、外国人材が法令に基づいて適正に働いていることを国に示すための大切な制度です。
定期届出は、所属機関が受け入れている外国人材の就労状況や生活支援の実施状況などを、一定期間ごとに出入国在留管理庁へ報告する義務のことです。
また随時届出もあり、契約変更や退職など特別な事由が発生した場合には、事由発生日から14日以内に提出しなければなりません。
年1回・4月15日提出
事由発生日から14日以内
定期届出は、従来は四半期ごと(年4回)の提出が必要でしたが、制度改正により年1回提出に一本化されました。これにより、提出の負担は軽減されつつも、引き続き外国人材の雇用が適正に行われているかを確認する仕組みが維持されています。
2025年4月15日提出分(2025年1〜3月分)が「最後の四半期定期届出」とされ、この提出をもって四半期制度は終了しました。その後は移行期間が設けられ、2025年4月から2026年3月までは定期届出の提出は不要です。
そして、2026年4月15日には「2025年4月〜2026年3月分」をまとめて提出する初回の年次定期届出が求められます。以後は毎年4月15日までに、前年4月から当年3月までの内容を年1回報告する方式へと切り替わります。

随時届出はどうなるんですか?



従来どおり必要です。むしろ定期届出が4半期から年1になる分、内部のチェック体制が緩みやすいので注意してください。
定期届出の年1回化の背景
定期届出は、なぜ四半期制から年1回制へ移行したのでしょうか。背景には「事業者の負担軽減」と「行政のモニタリングの効率化」があります。四半期提出は事務負担が大きく、現場からも「介護に集中できない」との声がありました。一方で、届出が形式的になり、実質的な監督につながらないケースもあったのです。
年1回制にすることで、行政は監督リソースを重点的に振り向けられ、事業者も「しっかりとしたまとめ」を提出できるようになります。ただし、年1回だからこそ、届出の精度や網羅性がこれまで以上に問われます。
随時届出(5区分)
随時届出とは、特定技能外国人の雇用や支援に関して「特別な事由」が発生した際にに出入国在留管理庁へ報告する義務です。
随時届出は、事由発生日から14日以内(暦日)に提出することが義務づけられています。休日を挟んでも延びないため、社内では「7日以内に起票する」ルールを持っておくと安全です。
出入管庁が公表している「運用要領(2025年4月1日改正後)」には、随時届出の流れを示したフローチャートが掲載されています。このフローチャートでは、随時届出が必要となる事由を大きく5つに分類しています。
提出期限:事由発生日から14日以内
- 特定技能雇用契約の変更・終了・新規締結(参考様式3-1系)
勤務日数や時間の変更、雇止め、契約更新なし、新規契約など。 - 1号特定技能外国人支援計画の変更(参考様式3-2)
夜勤有無の変更、担当部署異動に伴う支援体制の修正、生活支援や日本語教育方法の変更など。 - 登録支援機関への支援委託契約の締結・変更・終了(参考様式3-3)
委託の有無変更や契約先の切り替えなど。 - 受入れ困難(参考様式3-4)
施設閉鎖、経営悪化、災害、感染症による業務停止、無断帰国や行方不明。必要に応じて経緯説明書(5-11)、状況説明書(5-15)を添付。 - 不正行為の届出(参考様式3-5)
労働基準法違反や入管法違反などを把握した場合。



ん、なんだかたくさんありますね…



「契約に関することか」「支援計画に関することか」「委託契約に関することか」「退職や行方不明など受入が難しくなったことか」「不正に関することか」──この5つのケースに分けて考えれば迷わないですよ。
Case: 勤務日数を減らしたのに随時届出を忘れた
週5勤務を週4勤務に変更した施設。労働条件通知書を修正しただけで随時届出(3-1系)を怠り、後日入管から是正指導を受けました。



軽微な労働条件変更でも届出対象です。後追いは必ず発覚します。
Case: 登録支援機関を急遽変更した
委託先の支援機関が業務停止となり、急遽別の機関に切り替えたケース。届出(3-3)を怠ったため、支援体制の空白期間が生じ、改善指導を受けました。



バタバタして忘れました…。



支援委託契約は外国人の生活基盤に直結します。契約変更が発生したら最優先で届出してください。
Case: 突然連絡が取れなくなった
外国人職員が無断で帰国し、行方不明扱いとなったケース。受入れ困難(3-4)+経緯説明書(5-11)、必要に応じて状況説明書(5-15)を提出。
Case: 自己都合退職のみ
外国人本人が自己都合退職を申し出て、円満に退職。雇用契約終了の随時届出(3-1-2)のみで完了しました。
事業者: 本当に3-1-2だけで大丈夫?



本当に3-1-2だけで大丈夫ですか?



はい。ただし退職届や最終出勤日の記録を必ず保管してください。
Case: 複数同時退職が発生した場合
ある施設で3人の外国人が同時に自己都合退職を申し出たケース。全員分の3-1-2を個別に提出。提出期限は「各退職日の翌日から14日以内」で計算するため、まとめて処理しようとして遅れるリスクがありました。
罰則とリスク管理
届出を怠ったり虚偽を記載した場合は重大なリスクにつながります。行政指導→改善命令→罰則の流れがあり、さらに所属機関が欠格事由に該当すれば新規受入れができなくなります。
Case: 届出漏れで新規採用停止
随時届出を怠った施設が行政指導を受け、新規採用申請時に「欠格事由の可能性」とされました。一定期間採用ができず、介護現場は深刻な人手不足に。
Case: 虚偽届出のペナルティ
賃金を実際より高く記載して届出を行った施設が、後日労基署の調査で発覚。入管庁から改善命令と共に「虚偽届出による信用失墜」として厳しい是正を受けました。



嘘の届出は絶対に避けてください。小さな虚偽が法人全体の信頼を壊します。
届出漏れを防ぐには?



届出漏れを防ぐにはどうすればいいですか?



「仕組み化」することが不可欠です。
- 毎月「届出対象事由の有無」を点検
- 退職や雇止め・行方不明があれば即カウント開始(14日は暦日)
- 2026年4〜5月には2025年度分の年次定期届出を提出
- 電子届出システムを早めに登録し、省略要件を満たす
- 提出管理は「二重チェック」体制を取り入れる
Case: 担当者が休職して届出が漏れた
担当者が急に休職し、届出業務が滞ったケース。内部でバックアップ体制がなく、期限を過ぎてしまいました。



届出担当は「1人専任」ではなく、複数人が代替できるよう役割を分担しておくべきでしょう。
まとめ
特定技能制度は、介護分野における外国人材確保の柱として位置づけられています。現状の届出は、入管庁が定める様式を紙で作成し、管轄の入管局へ持参または郵送する形が基本です。ただし、今後は定期届出の年1回化を前提に、電子届出の普及や添付書類の省略条件が広がっていく予定です。
一方で、実地調査や立入検査は強化される見通しです。つまり「紙の届出の簡素化」と「実地監督の厳格化」が同時に進むことになります。事業者に求められるのは、形式的な提出ではなく、普段からの実質的な管理体制です。
採用後の届出は、定期届出(2026年から年1回)と随時届出(5区分)の二本立てです。定期届出は毎年4月15日が提出期限、随時届出は事由発生から14日以内に提出する必要があります。いずれかを怠ると、行政指導や受入停止といった処分につながる可能性があります。
届出の仕組みは、負担ではなく「外国人材の安心」と「施設の信頼」を守るセーフティネットです。改正によって形式は簡素化されましたが、その分「事業者の自律的な管理能力」が試されます。



届出は義務であると同時に、信頼を見える形にするツールです。更新や監査の場で自信を持つためにも、正確な運用を整えてください。



判断に迷うときはどうすればいいですか?



早めに専門家に相談することです。入管専門の行政書士なら最新の改正や運用を踏まえ、最適なアドバイスが可能です。
事業者にとって届出は「義務」であり「信頼を守る盾」。
制度を味方につけ、専門家の力も借りながら、介護現場と外国人材の未来を安定させましょう。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)