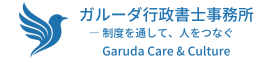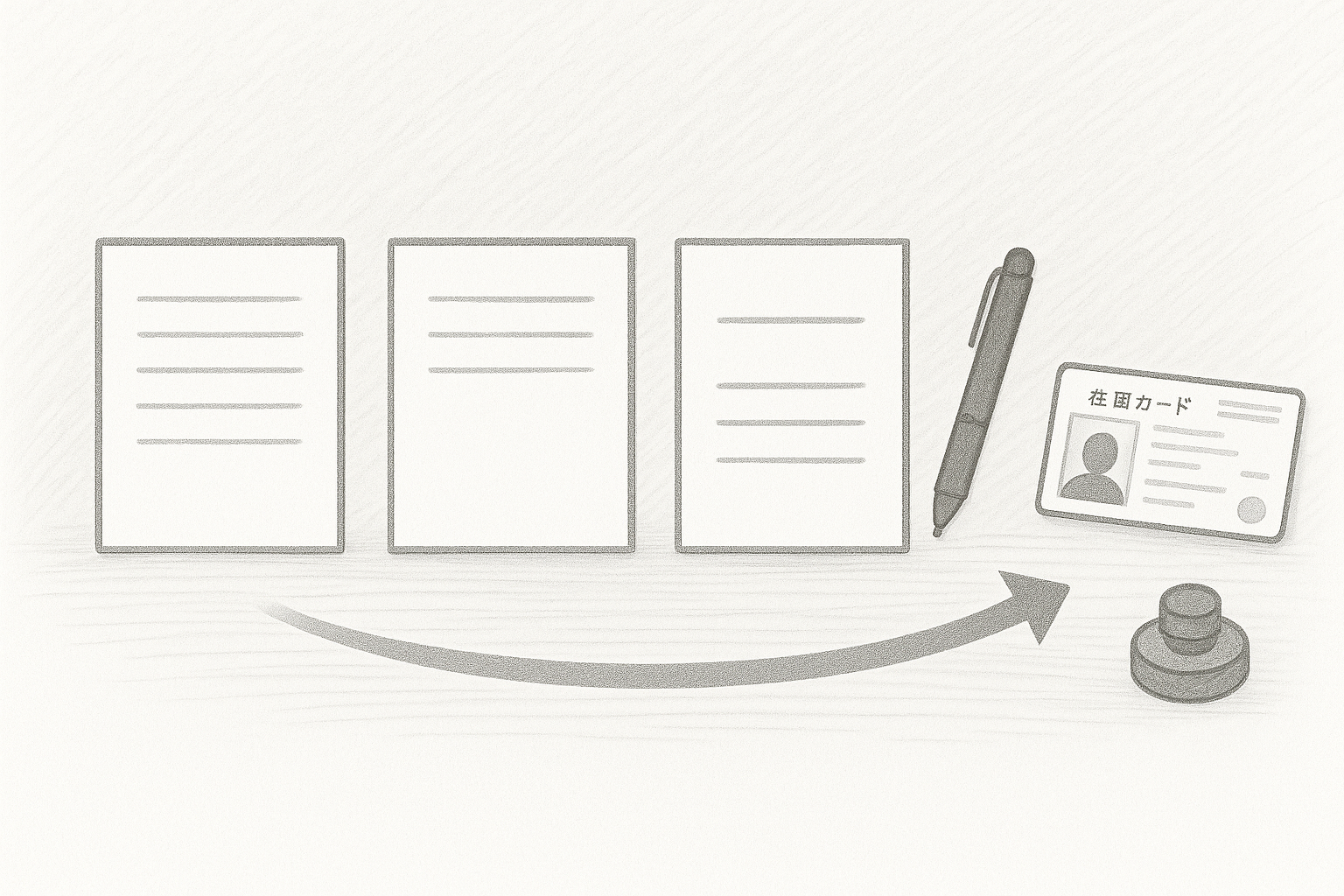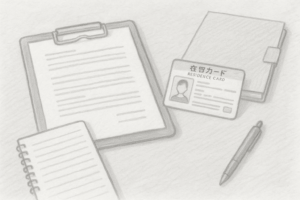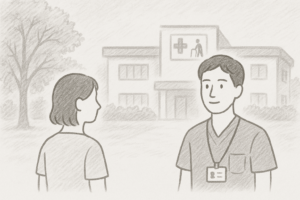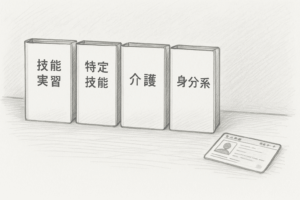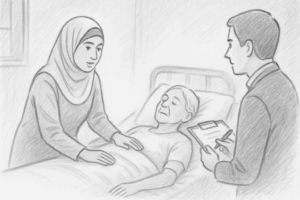特定技能「介護」で外国人材を受け入れている介護施設・事業所は、在留期間が満了するたびに「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。「契約を延長するだけ」と思って油断すると、申請が遅れて不法残留のリスクや、不許可になるケースもあります。
本記事では、更新申請の要件と必要書類、審査で注意されるポイントを整理し、よくある失敗と回避策を交えて解説します。
更新申請が必要となる場面
更新申請が必要なのは、次の場合です。
- 在留期間が満了し、引き続き雇用を継続する場合

雇用契約をそのまま延長するだけなら更新申請しなくてもいいのかな?



いいえ。在留資格には有効期限があります。在留期間が満了したときに雇用を続けたいなら、雇用契約を延長するだけでは足りません。在留資格は自動で延長されないので、必ず在留期間更新許可申請をしないと不法就労につながりますよ。
申請時期と提出先
- 提出先:所属機関所在地を管轄する地方出入国在留管理局
- 申請可能時期:在留期限の3か月前から申請可能
- 留意点:直前申請は補正や審査遅延で在留期限を迎えるリスクがあるため、余裕を持って準備することが重要



在留資格更新の手続きって、いつ頃から動き始めるのがいいですか?



3か月前から申請できます。期限直前だと審査が間に合わない可能性があるので、早めの準備が安全です。
必要書類一覧
特定技能申請の様式一覧(2025年4月改正)をもとにすると、更新申請で通常必要なのは以下の書類です。
| 書類名 | ポイント |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請書(特定技能・別記第17号様式) | 正確に記入。 |
| 雇用契約書(更新後のもの) | 前回契約との差異を明示。給与・勤務条件を具体的に記載。 |
| 支援計画書(最新版) | 前回の実績と整合。支援内容を具体的に。 |
| 事業所概要書 | 所属機関の体制・職員数・施設形態を最新化。 |
| 法人の登記事項証明書 | 代表者・所在地に変更があれば必須。 |
| 決算書・納税証明書 | 経営の安定性を示すために求められる場合あり。 |
| 在留カード・パスポートの写し | 本人確認用。 |



契約内容は去年と同じです。それでも契約書を出すんですか?



はい。入管は毎回、条件が前回と同じかどうかを確認します。
給与を下げたり、勤務条件を変えていれば、在留資格の適正性に影響しますし、外国人職員の保護のためにも重要な審査項目です。だから契約内容が変わらないなら「同じ」と分かる契約書を、変わっているなら変更点を明示した契約書を必ず出す必要があるのです。
書類作成の注意点
- 契約条件は「基本給◯円、夜勤手当◯円、残業代◯円」と具体的に。曖昧な表現は避ける。
- 支援計画は前回との整合性を確保。実績とのギャップは説明資料を用意。
- 登記事項証明書で法人の現状を反映(代表者変更や住所変更の見落とし注意)。
- 赤字決算でも直ちに不許可ではないが、改善見込みを示す資料や納税証明を添えて補強する。
よくある失敗と回避策
申請遅れで在留期限切れ寸前



在留カードが来週で切れてしまうんですが…



在留期間の満了前に更新申請をしていれば、申請が受理された時点で特例により審査中も現在の在留資格が有効と扱われ、日本での滞在・就労を続けられます。
在留期間が満了する前に更新申請をして受理されれば、審査中は特例により現在の在留資格が有効とみなされ、滞在・就労を続けることができます。とはいえ、万が一不許可となった場合にはその時点で在留資格を失い、直ちに不法残留となるリスクがあります。特例に頼り切るのは危険であり、在留カードの期限をしっかり管理し、少なくとも3か月前から更新準備を進めることが安全確実な対応といえます。
- 問題点:在留期限ぎりぎりでの申請は、特例により審査中は在留できるものの、不許可となった場合には即座に不法残留に。
- 回避策:在留カードの期限を一覧管理し、3か月前から準備する。
契約書があいまい



給与20万円以上と書けば大丈夫ですよね?



具体性が必要です。“基本給◯円、手当◯円”と明記しないと補正対象です。
- 問題点:曖昧な契約書は実態との不一致を疑われる。
- 回避策:具体的な契約条件を記載し、給与明細と一致させる。
契約書の記載が「給与20万円以上」など曖昧な表現だと、入管は「実際の支給額と一致しているのか」を疑い、補正や不許可のリスクが高まります。基本給・各種手当・残業代・勤務時間・休日などを具体的に記載し、実際の給与明細と齟齬がないように整えることが重要です。契約書の明確さは、外国人本人の安心にも直結します。
支援計画と実績が食い違う



計画は月1回の日本語研修でしたが、実際は2回しかできませんでした…



そのままでは“義務未履行”とされます。理由と改善策を添える必要があります。
- 問題点:支援計画と実績の乖離は審査で厳しく問われる。
- 回避策:支援実施記録を残す(出席簿、報告書、写真など)。次回計画は実行可能な内容に設定。
支援計画と実績が食い違うと「支援義務を果たしていない」と判断され、更新審査で不利になります。出席簿や報告書、写真などで支援の実施を証拠として残すことが不可欠です。また、計画が実行不可能な内容だと未実施扱いになりかねません。実績に即した計画を立てることが、審査通過と受入れ継続の鍵となります。
経営不安定と判断された



赤字決算ですが、大丈夫でしょうか?



改善見込みを示せば許可の可能性は十分です。複数期の決算書や納税証明を提出しましょう。
- 問題点:赤字や滞納は「安定性なし」と判断されやすい。
- 回避策:改善計画や納税証明を補強資料として提出。
赤字や納税の滞納があると、入管は「受入れを継続できる経営基盤がない」と疑う可能性があります。ただし、赤字だからといって直ちに不許可になるわけではありません。改善計画や納税証明、将来の収支見込みなどを提出すれば「継続可能性あり」と判断され得ます。複数期分の資料で改善の兆しを示すことが、リスク回避の決め手となります。
更新後の義務
更新許可が出た後も、所属機関には以下の義務があります。
- 契約・支援計画どおりに雇用・支援を継続
- 所属機関の変更(代表者・所在地など)があれば入管へ届出
- 定期報告を期限内に提出



更新許可が出ればホッとしますね。



確かに。でもね、更新許可はスタートでもあるんです。日々の支援と記録が、次回の更新を決めるんです。
在留資格更新のためのチェックリスト
在留資格更新申請は単なる「書類の差し替え」ではなく、所属機関の体制全体を見直す機会でもあります。入管審査では契約や支援の実態と整合しているか、経営が安定しているかといった点を細かく確認されます。
以下のチェックポイントを押さえておくと、直前に慌てることなく、安定した更新申請につなげることができます。
- □ 在留期限を一覧管理しているか
- □ 3か月前から更新準備を開始しているか
- □ 雇用契約書が具体的で、実態と一致しているか
- □ 支援計画と実績に整合性があるか
- □ 法人情報(登記事項証明書)が最新か
- □ 決算書・納税証明で経営安定性を示せるか
- □ 支援記録を残しているか
まとめ
在留期間更新は「ただの契約延長」ではなく、入管が改めて受け入れ体制を点検する機会です。契約内容が実態と食い違っていないか、支援計画どおりに生活支援や日本語学習が行われているか、所属機関の経営が安定しているか――これらはすべて審査対象になります。
実務の現場では「支援記録の整合性」「赤字決算時の補足資料」「申請時期の判断」など、対応が難しい局面もあります。こうした場合には、最新の制度改正や運用要領を踏まえた情報を確認しながら進めることが大切です。必要に応じて、入管手続きに詳しい専門家に相談するのも選択肢のひとつです。
補足:特定技能「介護」の更新で特に気を付けたいこと
特定技能「介護」の更新では、他の在留資格と同じように基本の書類を揃えることが大切ですが、介護分野ならではの注意点もあります。
- 在留期間は最長5年まで
特定技能1号は更新を重ねても通算5年が上限です。介護の仕事で5年を超えて働き続けるには、原則として、介護福祉士国家試験に合格し在留資格「介護」へ移行する必要があります。 - 雇用契約と実際の働き方が合っているか
給与・勤務時間・勤務地などが契約書と異なると、不許可になるリスクがあります。更新前に契約内容と現場の実態を必ず確認しておきましょう。特に介護分野では、次のような「不一致」が起こりやすいため注意が必要です。- 夜勤・シフト勤務
契約書に夜勤手当や勤務時間帯が明記されていないのに、実際には夜勤に入っているケース。 - 訪問介護業務の取扱い
契約上は施設勤務となっているのに、実際には利用者宅での訪問介護を行っているケース。 - 施設種別・勤務地の違い
契約書ではデイサービス勤務とされているのに、実際には特養やグループホームなど別の事業所で働いているケース。 - 業務内容の逸脱
「介護職員」として雇用されているのに、実際には清掃や調理など付随業務ばかりに従事しているケース。
これらの食い違いは更新時の審査で不適切と判断される可能性があります。契約内容と現場の働き方を定期的に点検しておくことが重要です。
- 夜勤・シフト勤務
- 支援体制が継続されているか
特定技能では、受入れ機関や支援機関が生活や就労のサポートを行うことが義務付けられています。更新時にも、その体制が適切に機能していたかが見られます。介護分野では、特に次のような点がチェックされやすいので注意が必要です。- 日本語での業務指導・生活支援
介護の現場では利用者との日本語コミュニケーションが欠かせません。日常的に日本語指導やOJTを行っていたか、支援記録を残しているかが問われます。 - 生活面での定着支援
夜勤シフトや不規則勤務が多い介護職員に対し、生活リズムや住居確保の支援が実際に行われていたか。特に深夜勤務後の体調管理に関する配慮なども含まれます。
- 日本語での業務指導・生活支援
- メンタルケア・離職防止の取り組み
介護現場は離職率が高く、ストレスも大きい職種です。孤立防止やメンタルサポートをどう行ったかが更新審査でプラスに働くことがあります。 - 転職や契約変更の手続き
受入れ機関が変わったり、契約条件を大きく変更した場合は、更新の前に必ず必要な届出や手続きを済ませておく必要があります。介護業界は離職・転職が多いため、実際にはここで手続きを漏らしているケースが多いです。例えば、特養から老健に移った、派遣契約から直接雇用に変わった、勤務地が別法人の施設になった、など。 - 制度改正のチェック
特定技能制度は見直しが多い分野です。申請前に最新の制度や運用を確認しておくと安心です。介護分野はその影響を受けやすく、実際に次のような改正・検討が続いています。- 訪問介護業務の可否(制度改正で一部解禁)
- 特定技能2号を介護分野に拡大するかどうかの議論
- 介護福祉士資格取得への支援策の追加
このようにルールが変わりやすいため、更新申請の直前には必ず最新の法務省・厚労省の公表情報を確認しておくことが大切です。



介護は勤務形態も特殊だし、支援も細かいから、在留資格更新申請でも見られるポイントが多いんですね。



そうなんです。介護ならではの現場の事情がそのまま審査対象になります。だからこそ、日常的に記録や体制を整えておくことが、安心した更新につながりますよ。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)