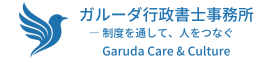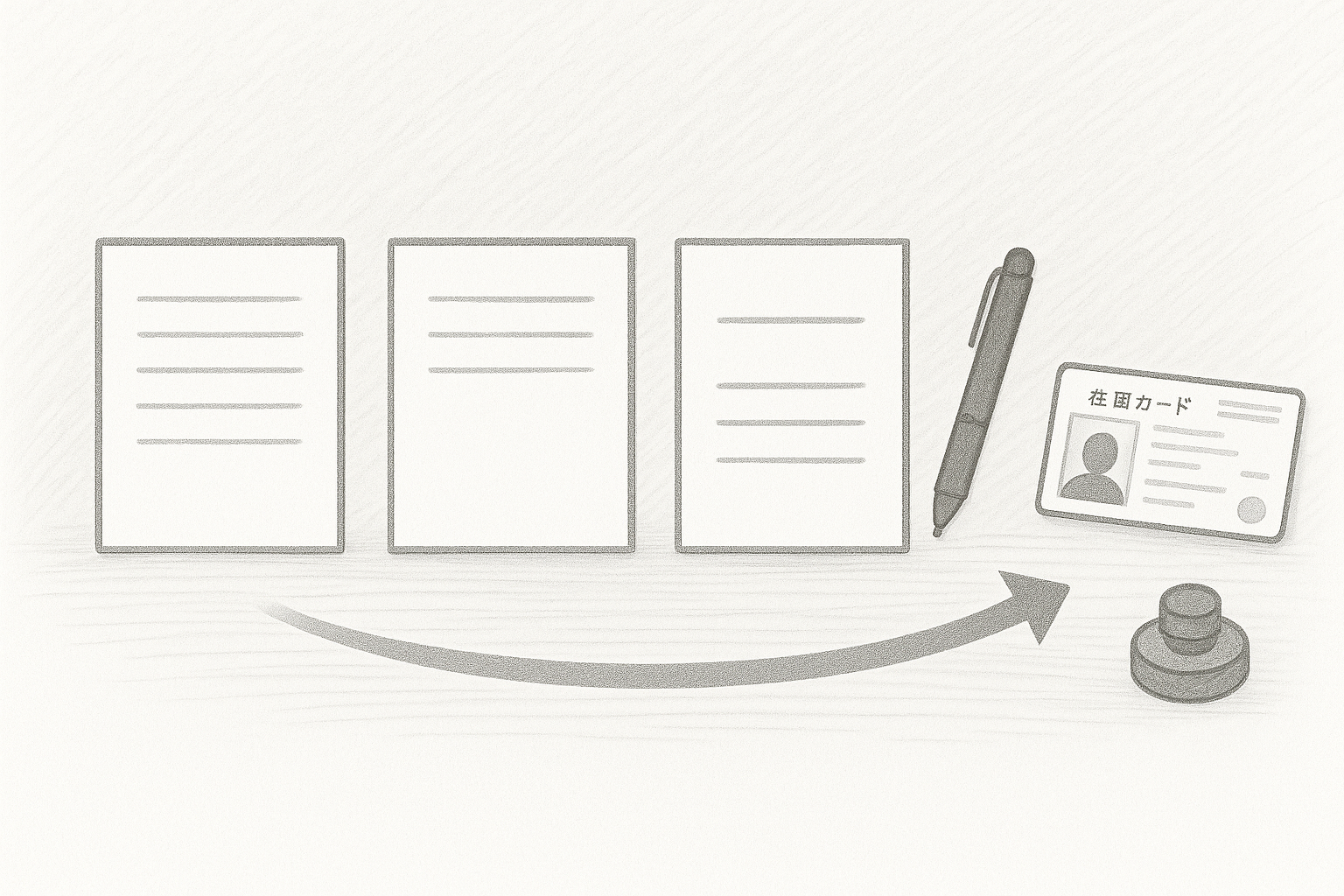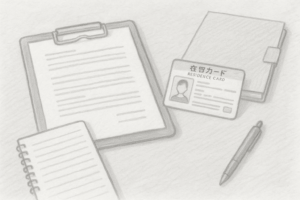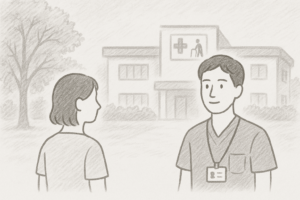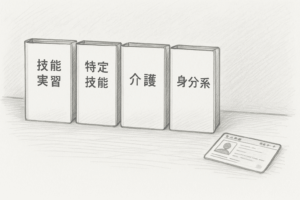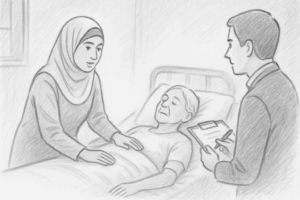特定技能「介護」で海外から人材を採用する際、最初に立ちはだかるのが在留資格認定証明書(COE)です。これは入管が「この人を日本に呼び寄せて就労させてもよいか」を事前に確認する仕組みであり、いわば入国の“前提条件”です。
ただし、COEが出てもそこで終わりではありません。COEをもとに査証(ビザ)を取得し、入国時に在留カードを受け取り、社会保険へ加入し、施設が生活支援を実行し、さらに各種届出をきちんと行って初めて「就労開始」となります。

COEは“切符”です。切符だけでは乗車できません。査証と入国という手続きを経て初めて、実際に働き始めることができるんです。
新規採用は、COEから入国後の生活立ち上げまで続く連続プロセスを理解してこそ成功します。
海外からの採用は原則、在留資格認定証明書(COE)で新規入国させる手続です。在留資格の変更は日本国内の手続であり、海外にいる段階ではできません。
ただし、有効な在留資格と(みなし)再入国許可が有効な一時帰国中の方は、COEではなく再入国し、再入国後に必要に応じて在留資格変更を行う流れになります。また、特定技能での再入国の場合、転職・入社など所属機関に関わる変更があれば、本人・受入機関ともに14日以内の届出義務があります。
採用準備:雇用契約・生活支援計画・所属機関の体制
雇用契約の締結
特定技能「介護」の外国人は労働者として受け入れます。したがって契約は労働基準法に沿い、日本人と同等以上の待遇であることが前提です。
- 賃金(基本給・手当)
- 勤務時間・シフト
- 休日・休暇
- 残業や夜勤の扱い
これらを正確に盛り込まないと、申請段階で補正を受けたり、後の更新で「契約と実態が異なる」と指摘される可能性があります。



技能実習のときの契約書を流用すれば早いですよね?



いいえ。実習は“OJT”、特定技能は“労働”。契約の性格がまったく違います。同じ書式では通りません。
生活支援計画の策定
生活支援計画は、入管がとくに注目するポイントです。単なる形式ではなく、外国人が安心して生活を始められるかを示す計画だからです。
支援の内容は以下のように具体化する必要があります。
- 住宅の確保と家具・家電の準備
- 日本語学習支援(頻度・教材・担当者)
- 生活オリエンテーション(銀行口座、携帯、交通ルール)
- 相談窓口の整備
抽象的に「支援する」とだけ書いても通りません。誰が、いつ、どのように行うのかが重要です。
所属機関の体制整備
施設側の適格性も厳しく審査されます。
- 経営が安定しているか(決算内容・納税状況)
- 社会保険への加入状況
- 分野別協議会へ加入しているか
ここが満たされていないと、申請自体が却下される可能性があります。
在留資格認定証明書(COE)
提出先と書類
申請先は就労予定地を管轄する地方出入国在留管理局。提出書類は多岐にわたり、法人関係・契約関係・本人関係の3セットをそろえるイメージです。
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 法人関係書類(登記簿、定款、決算書、納税証明)
- 生活支援計画書
- 本人の試験合格証明、日本語能力証明、パスポート写し など
書類は一つでも不備があれば補正指示となり、処理は長期化します。申請前にダブルチェックを徹底しましょう。
査証(ビザ)とCOEの有効期限
COEが交付されると、次は本人が母国で査証を申請します。必要書類はCOE原本、パスポート、申請書、写真など。
COEの有効期限は3か月。この期間内に査証申請と入国を終える必要があります。期限切れになるとすべて振り出しに戻り、再申請に数か月を要します。



COEが出たから一安心です。



いえいえ、まだ半分というところです。3か月のタイマーが動き出したと思ってください。
入国と在留カード
査証を取得して入国した際、空港で在留カードが交付されます(地域によっては後日郵送)。在留カードは就労資格を証明する唯一の公的カードであり、施設側はこれを確認し、記録として台帳に残す必要があります。
在留カードの確認を怠ると、更新時や監査で「在留管理が不適切」と指摘される可能性があります。
社会保険・雇用保険の加入
雇用契約を結んだ以上、健康保険・厚生年金・雇用保険は必ず加入させます。加入手続きは「遅滞なく」行うことが求められており、後回しは制度違反です。
社会保険未加入は更新時に大きなリスクとなり、「不適正な受入れ」と評価される事例が多くあります。
生活支援の実施
支援計画は書類で提出して終わりではなく、実際に実行しているかが後で確認されます。
住宅の契約が遅れてホテル暮らし、銀行口座が開設できず給与振込が遅れる、などはよくあるトラブルです。こうしたズレは本人の不安を招き、SNSなどで拡散されれば施設の信用問題に直結します。
支援は「実行+記録」が基本。支援を行ったら必ず記録を残しておきましょう。
届出義務
施設には、受入れ後も定期・随時・離職の届出義務があります。
- 定期届出:年1回、所属機関の体制や支援状況を報告
- 随時届出:契約条件や支援体制に変更があれば14日以内
- 離職届:契約終了時に必ず提出
これを怠ると「適正な受入れをしていない」と評価され、次回申請に不利となります。
よくあるトラブル事例
Case1:生活支援計画が抽象的すぎる
「日本語学習を支援する」とだけ書いた計画で申請。入管から補正指示が出て1か月遅延。現場は人員配置の再調整に追われました。



支援しますって書いてあるのに何が悪いんですか?



意思ではなく“実行可能性”を見られます。回数・方法・担当者まで具体的に書く必要があります
Case2:契約内容と勤務実態の不一致
契約書は「特養勤務」だったのに、実際は系列のデイサービスにも勤務。入管から「契約と実態が異なる」と指摘。更新時も「慎重審査」扱いとなりました。
Case3:管轄ごとの追加資料要求
東京では決算書2期分で受理されたが、大阪では3期分+納税証明を求められました。対応に2週間を要し、予定入国は延期。現場は夜勤体制で綱渡りのシフト運営に。
Case4:COEの有効期限切れ
本人の事情で査証申請が遅れ、3か月の有効期限を超過。COEは無効となり再申請。入国は半年後にずれ込みました。



有効期限があるなんて知らなかった…



COEは“切符”。切符には期限があります。施設側もカレンダーで管理してください
Case5:入国後の保険未加入
入国直後から勤務させたものの、社会保険加入を怠った事例。定期届出で「未加入」と指摘され、更新審査でもマイナス評価。雇用継続に支障が出ました。
Case6:生活支援の実行不足
計画では「住宅を提供」と記載したのに契約が間に合わず、本人はホテル暮らしに。本人は不安をSNSで発信し、施設の評判は傷つきました。採用力にも影響が出ました。
チェックリスト(海外から採用編)
新規採用の手続きは、COEから生活支援、各種届出まで複数の工程が連続しています。そのどこか一つでも漏れがあると、申請の不受理や入国遅延、さらには更新不許可につながりかねません。
実務担当者は日常業務に追われがちだからこそ、採用フローを一望できるチェックリストを活用することが重要です。ここで挙げる項目をひとつひとつ確認すれば、申請から受入れまでの抜け漏れを防ぐことができます。
- □ 雇用契約は労基法に適合、日本人と同等以上か
- □ 生活支援計画は具体的かつ実行可能か
- □ 所属機関の体制(経営・保険・協議会加入)は整っているか
- □ COE有効期限(3か月)を把握しているか
- □ 在留カードを確認し、記録管理しているか
- □ 社会保険・雇用保険に遅滞なく加入しているか
- □ 届出(定期・随時・離職)を適正に行っているか
- □ 訪問系サービス従事の要件(2025年4月改正)を把握しているか
おわりに
新規採用は「COE → 査証 → 入国 → 在留カード → 社会保険 → 生活支援 → 届出」という長いプロセスです。どこか一つでも疎かにすれば、採用は振り出しに戻り、現場は混乱します。



思った以上にやることが多いですね…



そうなんです。これは単なる書類仕事ではなく、受入れ体制の整備そのものですから。
特定技能「介護」は人材不足を補うだけでなく、介護現場に新しい力を与える制度です。最初の新規採用を丁寧に進めることが、安心できる受入れと長期的な信頼につながります。
日々の業務に追われながら複雑な申請や期限管理まで抱えるのは、施設にとって大きな負担になりがちです。そんなときは、入管専門の行政書士のような専門家の力を借りるのも一つの方法です。最新の法令や運用に基づき、抜け漏れなく進められるよう伴走してくれる存在がいれば、現場は本来の業務に安心して集中できます。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)