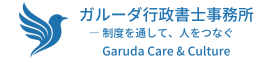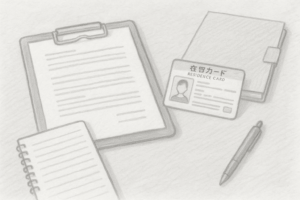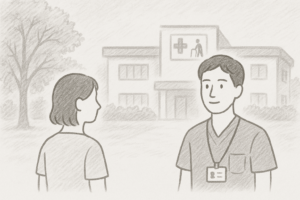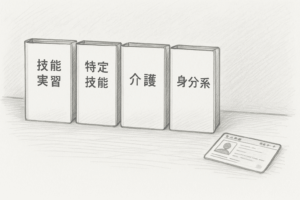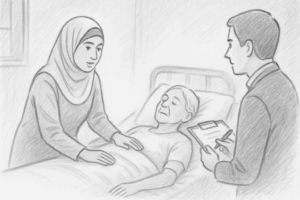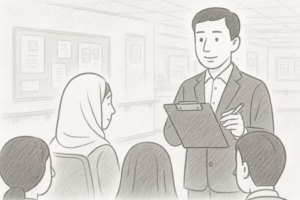※本記事は、2025年春以降に始まる「育成就労制度」への移行を前提にしています。
以下では、現行制度(2025年3月時点)の「技能実習」をもとに解説します。
新制度では「技能実習計画」が「育成就労計画」に置き換わるなど、一部の手続・用語が変更される予定です。
【出典:2025/3/11 閣議決定「特定技能・育成就労制度に関する基本方針」】
「技能実習制度が廃止される」──そんな報道が続く中、介護施設の受け入れ担当者の間では戸惑いが広がっています。
「もう外国人を雇えないのか」「在留資格はどうなるのか」。
制度の見出しばかりが独り歩きし、現場には不安と誤解が残りました。
実際には、制度が「終わる」のではありません。
外国人が日本で働きながら学ぶ仕組みは存続し、その理念を「国際貢献」から「人材育成」へ再設計する動きが進んでいます。
この見直しは「廃止」ではなく、制度疲労を整理し次の段階に進むための“再設計”と位置づけられています。

制度が廃止と聞いたんですが、今いる実習生はどうなりますか?



現行制度は経過措置で続きます。廃止ではなく、新しい仕組みに移行するんです。
介護分野に技能実習が導入された背景
技能実習制度が介護分野に導入された2017年からの7年間は、
制度の目的と現場の実態の間にどのような乖離があったかを最も端的に示す期間でした。
人手不足と制度導入の経緯
技能実習制度の起点は1993年。当初は「外国人研修・技能実習制度」として、開発途上国への技術移転を目的に始まりました。
しかし、実際には労働力確保の手段として利用されるケースが増え、不正防止の観点から2017年に「技能実習法」が施行されます。
このとき新たに導入されたのが、監理団体制度です。受け入れ企業や施設が適正に実習を行っているかを中立的に監督する仕組みでしたが、
その一方で、送り出し国と受け入れ先の間に複数の中間機関が介在し、構造が複雑化する副作用も生みました。
2010年代、日本の介護人材は慢性的に不足していました。
離職率は高く、特に地方では求人を出しても応募がない状態が続き、
厚生労働省は2025年時点で約32万人の介護人材が不足するとの見通しを示していました。
政府はこれに対し、外国人労働力の受け皿として技能実習制度を活用する方針を決定します。
EPA(経済連携協定)による介護福祉士候補者の受け入れは既に始まっていましたが、
国家試験合格を前提とした制度のため、実質的な担い手は限られていました。
より広範に現場人材を確保できる仕組みとして、2017年に介護職種が技能実習制度の対象に加わります。
制度上の目的は「介護技能の移転を通じた国際貢献」。
しかし現場が期待していたのは、即戦力としての人手確保でした。
この時点で、理念と実態の方向はすでに分かれ始めていたのです。



最初から“戦力”として期待してました。介護の理想よりも、現場を回すことが先だったんです。



その感覚は多くの施設で同じです。理念が現実に追いついていなかったんですね。
導入初期の課題と制度運用のずれ
制度導入当初、介護分野の受け入れ環境は十分に整っていませんでした。
教育カリキュラムや日本語研修の指針は後追いで整備され、
実際の指導は施設ごとに方法が異なり、監理団体も対応に苦慮しました。
監理団体は本来、不正防止と教育支援を担う仕組みでしたが、
実際には「書類確認中心の監督」にとどまり、教育現場への支援が届かない構造的限界を抱えていました。
制度設計の段階で、監理団体と実習実施者(介護施設など)の役割分担が曖昧だったためです。
受け入れ当初に頻発したのは、教育負担の集中と意思疎通の不全です。
利用者への声かけが伝わらず、職員が再説明を繰り返す。
記録や報告の書式も日本語で統一されており、指導時間が業務を圧迫しました。
地方の中規模施設では、初年度に3名のベトナム人実習生を受け入れました。
指導職員は通常業務に加え、毎日の教育記録を作成し、監理団体への報告書も求められました。
結果として、残業時間が増え、職員の一部が疲弊。
一方、実習生も「学ぶより作業をこなす」状態になり、
制度が想定した“技能の移転”はほとんど機能していませんでした。
このように、制度が掲げた教育目的と実際の運用との間に大きなギャップが生まれました。
監理団体は「実習計画の適正化」を形式的に確認するに留まり、
現場での教育や支援体制を評価・改善する仕組みは十分に機能していませんでした。
介護現場が直面した構造的な制約
技能実習制度では、実習生の在留期間は原則3年、最長でも5年です。
職場変更(転籍)は原則不可とされ、受け入れ先を離れると「失踪」扱いになる場合もありました。
この構造が、介護分野特有の課題を一層浮き彫りにしました。
介護の仕事は、利用者との信頼関係の積み重ねによって成り立ちます。
しかし、在留期限によってその関係がリセットされる。
施設にとっては人材投資が報われず、実習生にとっては長期的なキャリア形成が困難。
制度が掲げた「育成」と「継続」が、仕組みの上で両立していませんでした。



人手が足りなくて、最初から現場の戦力として期待していたんです。けれど、実際に一人で動けるようになるまで3年近くかかりますね。そして、ようやく戦力になったところで帰国なんです。



そこが制度上の限界です。技能実習は“定着”を前提に設計されていませんから、育てても関係が続かない構造になっていました。
制度が残した意義と課題
技能実習制度は、数多くの批判を受けながらも、慢性的な人手不足が続くなかで介護現場を支える役割を果たしてきました。
特に地方の施設では、実習生の存在が夜勤や身体介助などの業務を支え、
介護サービスの提供を継続するうえで欠かせない戦力となっていました。
制度が“現場を維持するための仕組み”として機能したことは否定できません。
しかし一方で、制度の本来目的である「技能の修得を通じた国際貢献」は十分に機能せず、
制度そのものの設計に起因する構造的な限界が次第に明らかになりました。
第一に、理念と運用の乖離です。
制度の理念は「技能を修得し、それを母国へ移転すること」でしたが、
実際には労働力確保の手段として運用されていました。
教育・訓練のための制度でありながら、現場では即戦力としての働きを求められ、
理念と現実の方向が大きくずれていたのです。
第二に、受入れ構造の複雑さです。
技能実習では、実習生が雇用主と直接契約を結ぶのではなく、
監理団体という中間組織を介して受け入れが行われます。
この間接的な構造によって、教育や労務管理の責任が分散し、
問題が発生しても改善の責任があいまいになりやすい仕組みになっていました。
第三に、実習内容と労働実態の乖離があります。
制度上は労働者ではなく、技能を修得する実習生として位置づけられていましたが、
実際の介護現場では実習というより労働そのものを担っていました。
このため、実習と労働の境界が曖昧になり、制度理念が現場の実態に追いつかない状況が続きました。
最後に、在留資格の非連続性です。
技能実習はあくまで「一定期間の実習を終えたら帰国する」前提の制度であり、
日本でのキャリア形成や長期的な定着を想定していませんでした。
せっかく日本語や技能を身につけても、
制度の期限が来れば帰国せざるを得ない構造が、現場の継続的な人材育成を阻んでいました。
これらの課題は、単なる運用上の不備ではなく、制度の理念・構造・在留設計そのものに起因する構造的制約でした。
制度が担った「人手不足を支える」という現実的役割と、
実習制度としての理念的枠組みが一致しないまま運用され続けた結果、
技能実習制度はその限界を制度自体の中に抱え込むことになったのです。
2023~2024年の政府有識者会議の最終報告では、
理念と実態の乖離が是正困難であること、在留資格の非連続性が人材定着を妨げていることが指摘されました。
その結果、政府は2025年、「技能実習制度を廃止し、新たな『育成就労制度』に移行する」方針を正式に示しました。
「出稼ぎ」ではない?理念と現実のはざま
技能実習はしばしば「出稼ぎ」と誤解されます。
制度上は教育・訓練を通じた国際貢献を目的としていますが、
送り出し国では手数料や借入を伴うことも多く、
現実には「生活向上のための就労機会」として受け止められています。
理念と現実のあいだのこの乖離こそ、制度が抱えた根源的な問題を象徴しているといえます。
まとめ:制度と現場をつなぐ視点
介護分野における技能実習制度の7年間は、
制度の理念と現場の運用のあいだにある距離を可視化した時間でした。
制度上の目的は「技能の修得を通じた国際貢献」でしたが、
実際には人手不足を補う仕組みとして機能し、
理念と現実の方向がすれ違ったまま運用されてきました。
技能実習制度が残した最大の教訓は、
制度と現実の間に生じるずれをどう埋めていくかという点にあります。
制度を設計する立場と、それを運用する現場のあいだには、常に時間差と理解の差があります。
技能実習制度の経験は、そのギャップを放置すれば制度が形骸化し、
理念が実態に追いつかなくなることを示しました。
法令の趣旨を現場に届かせ、現場の声を制度に反映させる――
その往復の仕組みをどう築くかが、次の段階に向けた課題です。
現在検討が進む「育成就労制度」は、
こうした構造的な矛盾を是正しようとする新たな枠組みです。
具体的な施行時期はまだ確定していませんが、
2027年4月1日施行案が有力視されている段階(案・見通しレベル)にあります。
理念を「国際貢献」から「人材育成」へと明確に転換し、
外国人が技能を高めながら継続的に働ける仕組みを目指しています。
制度が変わろうとしている今、
問われているのは、その制度を通じてどんな社会をつくるのかという視点です。
これまでの技能実習制度は「国際貢献」を掲げながら、
実際には人手不足を補う仕組みとして運用されてきました。
これからの制度には、外国人が働きながら成長し、
日本社会の一員として力を発揮できる環境づくりが求められます。
「働く外国人をどう育て、どう支えるか」――
その問いに、制度と現場の双方からどう応えていけるかが、
これからの外国人材受け入れ政策の方向を決める鍵となります。
次回は、介護分野で実際に技能実習を導入する際の手続きと現場準備を整理します。
採用ルールや人数枠、監理団体との契約、技能実習計画の申請手続きなど、
制度を「理念」から「実務」へとどうつなげていくのか――
現場の運用の流れを具体的に見ていきます。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)