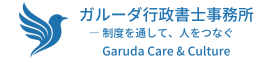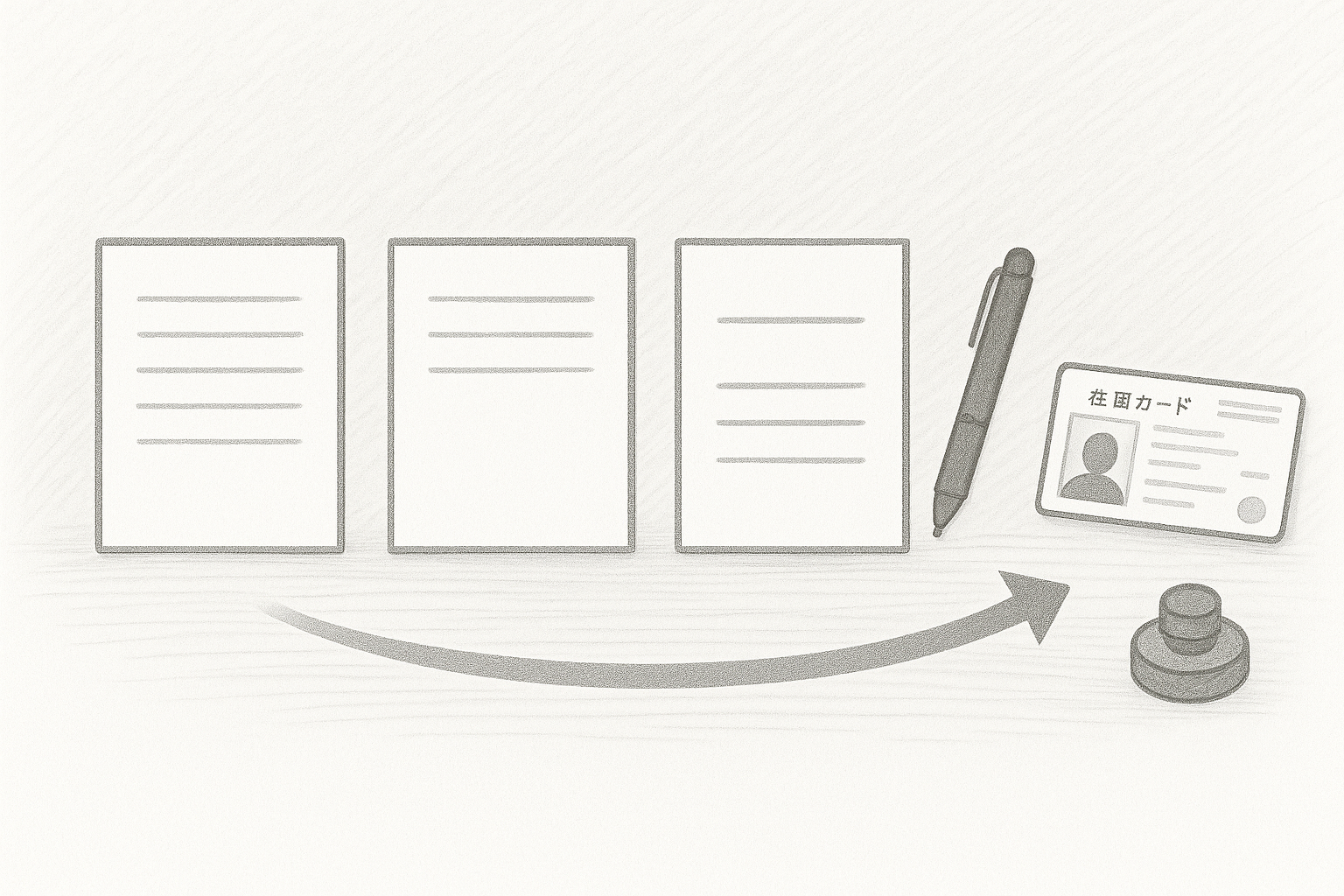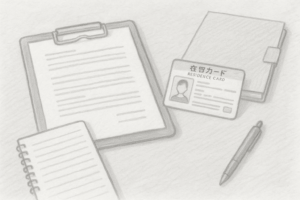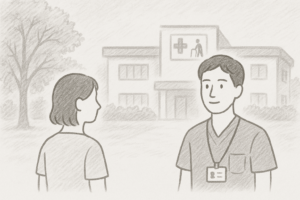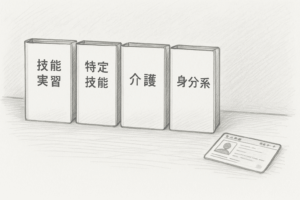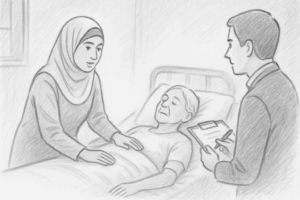特定技能「介護」で外国人を採用する方法には二つあります。海外から呼び寄せる方法と、すでに日本に在留している外国人を採用する方法です。前回は海外採用の流れを取り上げましたが、今回は「国内採用」のケースを解説します。
国内採用は大きく二つのパターンに分かれます。在留資格の変更が必要な場合と、変更が不要な場合(同じ特定技能「介護」内での転職)です。それぞれ手続きや提出書類が異なるため、採用前にしっかり確認しておくことが重要です。
- 在留資格の変更が必要な場合
留学生 → 特定技能「介護」/技能実習修了者 → 特定技能「介護」/特定技能「外食など」 → 特定技能「介護」
→ 手続き:在留資格変更許可申請 - 在留資格の変更が不要な場合
特定技能「介護」から特定技能「介護」
→ 手続き:本人と受入機関が14日以内に届出
→ 必要に応じて在留期間更新
在留資格の変更が必要なケース
技能実習修了者
介護分野の技能実習を良好に修了した者は、試験免除で特定技能「介護」へ移行できます。修了証明書の提出が必須であり、実習中の勤務評価や指導記録が悪ければ審査に不利になる場合があります。
留学生
介護福祉士養成施設を修了した留学生、または介護技能評価試験と日本語試験に合格した留学生が対象です。卒業見込みでは申請できず、卒業証明書や合格証明書を提出できる段階で初めて申請可能となります。

留学生で日本語が堪能な人材がいます。卒業見込みですが、採用できますか?



残念ながら、卒業見込みではだめなんです。入管は“申請時点で要件を満たしているか”を確認します。卒業証明書を取得できる状態になってから申請しましょう。
EPA介護福祉士候補者修了者
EPA(経済連携協定)による介護福祉士候補者としての研修を修了した外国人も、国内採用の対象に含まれます。
その他の在留資格からの切替
家族滞在や短期滞在などから特定技能「介護」へ切り替える事例もあります。ただし、技能評価試験と日本語要件を満たしていることが前提です。
他分野の特定技能からの切替
外食・建設など他分野の特定技能で在留している外国人が、介護分野へ移る場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。同一分野内(介護→介護)の転職は届出で足りますが、分野をまたぐ場合は必ず資格変更許可申請になります。



外食分野の特定技能で働いていた方を介護職に採用したいのですが、そのまま受け入れできますか?



同じ特定技能とはいえ、分野が違うので資格変更許可が必要です。新しい雇用契約書や支援計画書を添付して、申請を行います。
提出先と必要書類(在留資格変更が必要な場合)
申請は本人住所地を管轄する入管局に提出します。
共通して必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 支援計画書
- 事業所概要書
- 所属機関の登記事項証明書・決算書
- 介護分野特定技能協議会の加入証明
- パスポート・在留カード
- 顔写真(4cm×3cm)
- 収入印紙4,000円
技能実習修了者からの切替の場合
- 技能実習修了証明書(OTIT発行)
- 実習中の成績評価関連書類(不良記録がないことの確認に利用される場合あり)
留学生からの切替の場合
- 卒業証明書(介護福祉士養成施設等)
- または介護技能評価試験合格証明書+日本語試験合格証明書
- 地域によっては成績証明書の提出を求められるケースもある
EPA介護福祉士候補者修了者からの切替の場合
- EPA研修修了証明書
- 必要に応じて介護技能評価試験の合格証明書
その他の在留資格からの切替の場合
在留資格ごとの裏付け資料(例:扶養関係を示す書類など)
介護技能評価試験合格証明書+日本語試験合格証明書
在留資格の変更が不要なケース(特定技能「介護」から特定技能「介護」への転職)
すでに在留資格「特定技能『介護』」を持っている人が、同じ介護分野の別の受入機関へ転職する場合は、在留資格の変更は不要です。「特定技能運用要領」にも明記されているとおり、同一分野内の転職は資格変更ではなく届出で対応します。
ただし、本人と受入機関の双方に義務があります。
- 本人の届出義務:「契約機関に関する届出」を転職後14日以内に地方出入国在留管理局へ提出(遅延は不利益処分の対象)。
- 受入機関の届出義務:「所属機関等に関する届出」を提出。
- 在留期間更新:在留カードの残存期間が短い場合は「在留期間更新許可申請」を併せて行う。
支援計画は転職のたびに新たに作成が必要で、形だけの計画では補正指示や不許可につながります。



「うちに転職してきたい特定技能『介護」の方がいます。資格変更の申請が必要ですか?



同じ介護分野であれば資格変更は不要です。ただし、届出の提出や支援計画の作成は必要なので注意が必要です。
トラブル事例
留学生のケースでありがちなのが、卒業証明書が発行される前に資格変更を申請してしまうことです。入管は「申請時点で要件を満たしているか」を厳格に審査するため、卒業見込みでは不許可となります。防ぐには、契約や支援計画を先に整えておき、卒業証明書が出たタイミングですぐ申請できる準備を進めることが大切です。
技能実習修了者が特定技能「介護」へ移行する際、技能実習修了証明書がなかなか届かず、在留期限に間に合わなかった例があります。この場合、やむなく帰国を余儀なくされることもあります。申請者本人だけでなく受入機関も、修了予定時期を確認して早めに発行依頼をかけておくことが肝心です。
契約書には「日勤中心」と記載されているのに、実際には夜勤ばかりというケースがありました。入管は契約内容と実態の整合性を重視しており、不一致は「虚偽申請」と見なされかねません。後にシフトが変わる予定なら、契約書に反映するか、変更契約を準備しておく必要があります。
所属機関が「介護分野特定技能協議会」への加入を済ませておらず、協議会加入証明を添付できなかったため、申請が差し戻された例です。協議会加入は必須要件であり、加入証明がなければ申請は受理されません。採用前に必ず加入手続きを完了し、証明書を取得しておきましょう。
支援計画に「生活支援を行う」とだけ書き、具体的な内容が欠けていたため補正指示を受けた例です。銀行口座の開設サポートや医療機関受診への同行、日本語学習支援などを具体的に記載する必要があります。入管は「実効性のある支援が可能か」を見ています。
特定技能「介護」の資格を持つ人が転職後に届出を怠った結果、在留資格更新時に不許可処分を受けた事例もあります。届出は転職後14日以内と明確に定められており、本人も受入機関も連携して必ず期限内に対応する必要があります。最悪の場合、資格取消しにつながるため軽視は禁物です。
まとめ
国内採用には二つのルートがあります。留学生や技能実習修了者などからの採用は在留資格変更許可申請、すでに特定技能「介護」を持っている人の転職は届出で対応できる。どちらのケースでも見落としやすい実務の落とし穴があるので、細部まで注意が必要です。
さらに、特定技能「介護」をめぐる制度は変化を続けています。試験合格者が増えて採用の主流になりつつあることや、訪問系サービスへの従事が解禁されたことはその典型です。「以前はこうだった」という感覚で進めると、思わぬ失敗を招く可能性があります。
行政書士に相談すべき場面
在留資格の申請は形式だけでは通りません。タイミングや書類の不備があれば即不許可のリスクもあります。例えば――
- 卒業や修了のタイミングがぎりぎりで申請時期に迷うとき
- 契約内容と勤務実態に食い違いが生じそうなとき
- 支援計画の書き方がわからないとき
- 協議会加入や保険加入など、所属機関の体制に不安があるとき
- 実習中にトラブルがあった人材を採用したいとき
- 特定技能「介護」から転職してくる人の届出や支援計画をどう扱えばよいか判断がつかないとき
- 訪問系サービスへの従事を予定しているが、要件に適合するか不安なとき
こうした場面では、行政書士に相談することで最新の運用に即した安全な対応が可能となります。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)