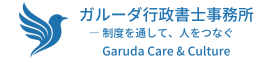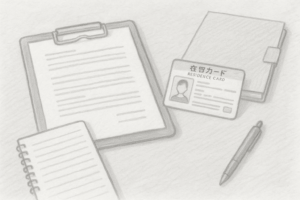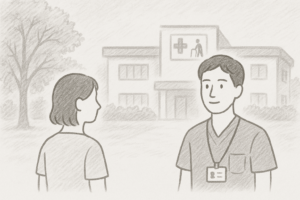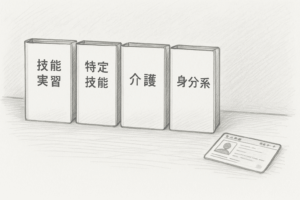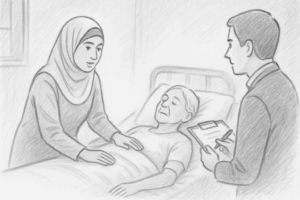介護現場では深刻な人材不足が続いています。高齢化の進行と人材確保の難しさは、もはや施設経営にとって避けて通れない課題です。こうした状況を背景に、2019年に新たに創設されたのが「特定技能」という在留資格。そのなかでも特定技能「介護」は、外国人材が日本の介護現場で即戦力として働くことを可能にした制度として注目を集めています。
本記事では、特定技能「介護」制度の背景から仕組み、そのメリットと課題、さらに他の在留資格との違いまでを解説します。まずは全体像をつかみ、制度活用に向けた基礎知識を身につけましょう。
制度創設の背景
日本の介護分野は深刻な人材不足に直面しています。高齢化が急速に進む一方で、介護現場で働く日本人職員の確保は年々難しくなっています。厚生労働省の推計では、今後さらに数十万人規模の人材が不足すると見込まれています。
このような課題を受け、日本政府はこれまでにも外国人材の受け入れを進めてきました。代表的なものが「EPA(経済連携協定)による介護福祉士候補者の受け入れ」と「技能実習制度」です。しかし、EPAは対象国が限られており、国家試験合格という高いハードルがありました。技能実習制度についても、本来「技能移転」を目的としているため、介護人材を長期的に確保する仕組みとしては十分ではありませんでした。
このように従来の制度だけでは介護人材不足を解消できないという問題意識から、2019年4月に出入国管理及び難民認定法が改正され、新たに創設されたのが「特定技能」という在留資格です。その中の一分野として位置づけられたのが 特定技能「介護」 です。

なるほど…EPAや技能実習だけじゃ不足だったんですね。



はい。その弱点を補う形で、特定技能『介護』が導入されたんです。
特定技能の概要
特定技能とは
特定技能は、人材不足が特に深刻な14分野を対象として創設されました。建設、農業、宿泊、外食など多岐にわたり、介護分野はその中でも最大規模の受入れ見込みが示されています。
特定技能には原則として、「1号」と「2号」があります。
1号と2号の違い
- 特定技能1号:相当程度の技能を持つ外国人が対象。全分野通算で5年まで在留可能。家族帯同不可。特定技能「介護」はここに含まれます。
- 特定技能2号:熟練技能を持つ外国人が対象。更新制限なし、家族帯同可。ただし介護分野は対象外です。



えっ、2号がないんですね…。とすると、特定技能「介護」1号が終わった後はどうなるんですか?



介護分野は2号がありません。その代わり、介護福祉士資格を取れば『在留資格:介護』に移行できます。
労働条件と受入れ基準
特定技能「介護」の特徴は、即戦力として雇用できること。法律で「日本人と同等以上の報酬」が義務付けられており、社会保険適用や法令遵守、さらに『1号特定技能外国人支援計画』の策定が求められます。



へぇ、そうなの?外国人でも日本人と同じお給料を払わないといけないんですか?



はい。『同等以上の報酬』が法律上の要件です。よく誤解されていますが、外国人を安く雇える制度というわけではないんです。
外国人介護人材受け入れの流れ
入国前
特定技能「介護」では以下3つの試験合格が必要です。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) または 日本語能力試験(JLPT N4以上)
- 介護日本語評価試験
- 介護技能測定試験
合格後、介護施設と雇用契約を結び、在留資格認定証明書交付申請書を提出します。



そんなに?日本語の試験だけじゃなくて他にも試験があるんですか?



はい。日本語+介護日本語+介護技能の3つの試験合格が必須です。
入国後
入国時に在留カードが交付され、就労開始となります。所属機関はオリエンテーションを行い、生活や職場環境に適応できるよう支援します。
支援体制
受入れ機関には「生活支援計画」の策定をはじめ10項目の支援義務があります。住居探しや生活相談などは登録支援機関に委託も可能で、一定要件を満たす場合には免除規定もあります。
従事可能な業務
主に介護施設での身体介護・生活援助・機能訓練補助など幅広い業務に従事可能です。
特定技能「介護」のメリットと課題
介護現場のメリット
- 慢性的な人材不足の解消
- 即戦力の確保によるサービス安定化
- 外国人材の多様性が職場や利用者に与えるプラス効果
外国人本人のメリット
- 日本人と同等以上の報酬が保障される
- 国籍を問わず利用可能
- 実務+養成校等を経て介護福祉士国家資格合格 → 在留資格「介護」へ移行が可能
課題
- 現場で求められる日本語力と制度上の基準(N4)のギャップ
- 文化・生活習慣の違いによる定着の難しさ
- 受入れ機関の体制整備コスト



N4って、確か、基礎的な日常会話ができるレベルですよね?現場で働くには不十分なんですか?



介護の現場では“排泄”“嚥下”“褥瘡”など専門用語や、利用者さんの微妙な言い回しを理解する力も必要です。大変ですよね。
他の在留資格との比較
類似の在留資格との違いも簡単に確認しておきましょう。
- 技能実習:技能移転を目的とする制度で、最長5年。長期的な定着やキャリア形成には不向き。
- 育成就労:政府が導入方針を示している新制度。技能実習に後継として創設される在留資格で、就労を通じて技能を育成し、必要に応じて特定技能へ移行できる仕組みがある。ただし、2025年9月時点で制度の施行時期や具体的内容は未定。
- 介護:介護福祉士国家資格を持つ外国人が対象。在留更新制限なし・家族帯同可能。専門職として日本に長期定住できるルート。



技能実習と特定技能って似てませんか?混乱するなぁ…。



技能実習は“技能を学ぶための実習(OJT)”、特定技能は“労働”です。この違いが大きいんです。
以下では、分かりやすく表にまとめました。
| 在留資格名 | 主な対象 | 在留期間 | 家族帯同 | 制度の目的 | 特徴・位置づけ |
|---|---|---|---|---|---|
| 技能実習 | 技能移転を目的とする実習生 | 最長5年 | 不可 | 技能習得・帰国後活用 | 本来はOJT目的。長期の労働力確保には不向き |
| 育成就労(新制度) | 技能実習の後継制度(導入方針あり、施行時期未定) | 移行期間あり | 不可 | 就労を通じた技能・知識の育成 | 特定技能へのステップアップも可能 |
| 特定技能「介護」 | 試験合格者(JFT-Basic/JLPT N4+介護日本語+介護技能) | 通算5年(全分野合算) | 不可 | 即戦力人材の就労 | 幅広い国から受入れ可能。介護人材不足に直接対応 |
| 介護ビザ(在留資格「介護」) | 介護福祉士国家資格者 | 更新制限なし | 可 | 専門職としての就労 | 長期定住や永住につながる制度 |



特定技能の在留期間は5年か…。5年だけじゃ短い気がしますね。



5年の間に介護福祉士資格を取得すれば、在留資格『介護』で長期就労が可能になりますよ。



そうか!在留資格『介護』であれば、更新制限がないから、期間の定めなく働いてもらうこともできるんですね。
特定技能「介護」は「介護福祉士資格がなくても、試験合格で入国し現場で即戦力として働ける制度」です。
育成就労や技能実習が「入口手前の準備段階」であるのに対し、特定技能「介護」は「介護キャリアの本格的なスタート地点」として重要な役割を担っています。
外国人介護人材のキャリアパスのイメージ
技能実習(現行/将来は育成就労)
│
↓
特定技能「介護」(最長5年・即戦力)
│
↓
介護福祉士国家資格 合格
│
↓
在留資格「介護」
(更新制限なし・家族帯同可)
今後の展望
特定技能「介護」は2019年の制度創設から数年が経ちましたが、実際の受入れ人数は当初の政府目標である「5年間で6万人」に届いていません。その背景には、試験の複雑さ、手続きの煩雑さ、受入れ機関の支援体制不足、さらには外国人本人の日本での生活・文化適応の難しさなど、複合的な要因があります。
一方で、日本の介護分野における人材不足は今後も拡大する見込みです。政府は制度の見直しや支援体制の強化を進めており、外国人材のより円滑な受け入れと長期的な定着が期待されています。
ただし、介護分野には特定技能2号が設けられていません。これは、介護福祉士資格を取得して『在留資格:介護』に移行することを前提とした制度設計だからです。
特定技能「介護」は国家資格取得への中間ステップとしての性格が強く、今後は介護福祉士資格を取得しやすくする支援や仕組みづくりが、制度の成果を左右する大きなポイントとなるでしょう。
まとめ
特定技能「介護」は、日本の深刻な介護人材不足に対応するために新たに創出された在留資格です。
- 即戦力の人材を受け入れる制度であり、日本人と同等以上の報酬や社会保険加入が義務付けられています。
- 入国には「日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4)」「介護日本語評価試験」「介護技能評価試験」の合格が必須です。
- 従事できるのは介護保険法に基づく施設・事業所
- 在留期間は最長5年ですが、その間に介護福祉士国家資格を取得すれば「在留資格:介護」へ移行でき、長期在留や家族帯同も可能となります。
特定技能「介護」はゴールではなく、「介護人材としてのキャリアを築くためのスタート地点」。受け入れる施設にとっても、働く外国人にとっても、この資格をどう活用し、介護福祉士資格や長期定着につなげるかが成功のカギになります。



詳しく聞いたら、自分たちだけで進めるのは難しい気がしてきました…



入管手続きは複雑で、改正も多いです。事業者様が自分たちだけでやるのは現実的ではないかもしれません。専門家と一緒に準備するのが確実です。
🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い
本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。
実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。
現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。
お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。
ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。
✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com
(件名に「介護現場の声」とご記載ください)